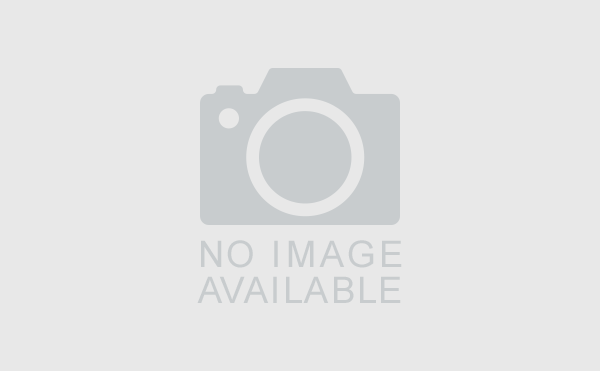かじってみよう社会学Ⅱ第6講『意識から地域が薄れていく』
小学校の学習発表会(以前の学芸会?)に行ってきました。全部を見たわけではないのですが、孫が小学校5年生ということで、五年生の発表を見てきました。約20分の渡りこれまで学習したことの発表でした。野外活動でクラスの仲間意識が強まったとか、遠足で新たに知ったことに興味関心が深まった等々語られていました。成長を実感する様子にお祖父さん目線になってしまいました。
そんな中で驚いたのは、様々な場面で「地域のために」「地域に感謝」という言葉が出てくるのです。もちろん担任の先生が原稿を書いて、それを子どもたちが自分の言葉として語っているのだろうとは思うのですが、それでも指導要領を逸脱した内容を語らせているとは思えないので、子どもたちの教育内容が、「地域のために」「地域に感謝」を指導しているのだと思います。
現在、特に小学生の若い親御さんは、一般的な言い方になりますが、余り「地域」には関心を持たず、子どもたちは、学校、塾、スポ小等々との往復の時間の中でだけの暮らしになっています。そんな親御さんに「地域のために」「地域に感謝」という子どもたちの言葉は、とても大きな意味を持つように感じたのです。そばにいた校長先生には、感じたままの感想をお話しさせてもらいました。
この様なことから、改めて私たちの意識の中から「地域」が薄れてきているのはなぜなのだろうかと考えてみました。振り返ってみると、急激に地域が意識されなくなっているような気がしています。2年前に、四国八十八ヶ寺歩きお遍路をした時、愛媛県に入ったとたん集団登校している様子が目に入りました。仙台に戻ってから調べてみると、集団登校している学校がとても多かったのです。宮城県とは全く比較になりませんでした。それぞれ地域特性があるので、一概には比較できませんが、その違いに驚いてしまいました。この例から考えてみると、単に時代の違いだけでは内容にも感じます。
「地域」という言葉の多様性を持っています。地域社会、地域生活、地域問題、地域医療、地域防災、地域福祉、地域住民 等々、「地域」は、日常生活において重要な意味を持つ言葉になっています。ところが、使われた文脈の中の位置づけは、厳密に理解しようとすると、とたんに壁にぶち当たります。
日常用語としての「地域」は雑然としています。その理由は、使われ方の「多様性」にあります。更には、この特性に加え「地域」という言葉は、その空間的範囲が曖昧模糊としていのです。話し手、聞き手の間で、理解に併せて都合良く、自在に空間的範囲を縮小/拡大して聞き話します。この為、「地域」と言う言葉は、多様性に加え「多重性」をも持っているのです。
こうした個々人の受け止め方で認識の異なる地域は、「地域」は、明らかにその重要性を低下させています。人々の行動空間範囲は、これまでの「地域」という狭い範囲を大きく超え、また、一日の生活時間配分も、「地域」の中で過ごす時間を大幅に縮小させています。
また、人々が日常生活の中で、「地域」に関わる機会が減少するに伴い、「地域」に抱いていた実感としての重要性もまた薄らいます。生活の空間的範囲は、「地域」を超えて営まれ、生活時間もその多くが「地域」外で費やされ、その結果、生活の中で「地域」の手応えのなさを実感しているのです。このことは、若者層に顕著で地域に関心を持たない背景にもなっています。このことは、『無用性実感の拡大』と表現されています。
「地域」の無用性実感の拡大は、住民の「地域」への関与の低下とストレートに結びつきます。匿名性空間の拡大という事態を起因にしつつ、益々偏りを大きくしています。また、このことは共同の生活問題に対する住民の共同処理の大幅な縮小という事態とも相応しています。地域住民が総出で清掃を行うということへの不参加などもこの傾向に加わってきます。
住民の相互扶助による処理を出来るだけ省略し、専門処理に高度に依存する生活を営むことを「都市的生活様式」と表現されます。いわゆる従来近隣関係で営まれていたことがアウトソーシングするということです。冠婚葬祭などは誰もが関わり想像しやすいと思います。従来は、地域の契約講などで行われていましたが、現在は葬儀屋さんに一切をお任せして営まれます。
行政や市場への依存度が高まれば高まるほど、「地域」への住民の関与は益々縮小していきます。このことは、お互い様の機会(互酬性)や贈与交換の減少という生活状況にも現れています。
では、なぜ地域住民による共同処理の大幅な縮小という事態が生じたのでしょうか。共同処理の大幅な減少は、『家族構成の変化に伴って生じた』と言われています。1950年代から80年代前半に掛けては、直系家族の制度的形態としての「イエ(家)」から「夫婦家族」へと、その構成を少しずつ変化させていった(核家族化への変容)のです。現在の団塊の世代の方々の時です。現在は、高齢夫婦二人世帯が増加し、人口が減少する中にあって世帯数だけが増加する家族構成の変化が生じています。
「地域」とのつながりの変化は、「イエ(家)」という半開放的家族システムから「夫婦家族」という閉鎖的家族システムへの変化に起因しています。閉じた小家族の大量出現は、産業化や都市化とあいまって、多様な地域集団の成立それ自体を危うくさせているのです。核家族化は、夫婦家族のメンバーと地域集団とのつながりを衰弱させる事を通じて、家族と「地域」との結びつきを希薄化し、住民による共同処理の大幅な縮小をまねいたのです。
こうしてみると、地域に対する無関心は、それぞれ個々人の意志に寄ることではないのが分かります。私たちは、地域活動に対する昨今の関心低下を個々人の意識にその原因を置いている傾向にありますが、決して本人の無関心だけの問題では無く、社会の有り様がその様にさせているのです。私たちは、『地域づくり』と言ったとき、本人の意識だけを問題とするのではなく、地域社会の有り様にも目を向けて対策を考えていかなければいけないのです。
私たちが暮らす地域社会では、従来に無かった課題が生じています。環境問題への関心、防災・防犯に関する事案の日常化、介護問題の深刻化。また、社会保障の財源問題から地域医療・地域介護の推奨等々、個々人の単位では対応が難しい課題が出ています。従来の共助と異なる今日的な共助は必須になってきているのです。私たちは、こうした新たな共助社会を構築して行く必要に迫られています。この矢面に立つのが、現在子育てそして介護に関わり現役世代に皆さんです。この様な視点から、地域社会の有り様を考えていくとき、その担い手のあり方に大きな変化が生じるのでは無いかと思います。現在の高齢者を中心とした町内会(伝統的自治活動)なども、この視点至ったとき、新たな展望が開けるのではないでしょうか。