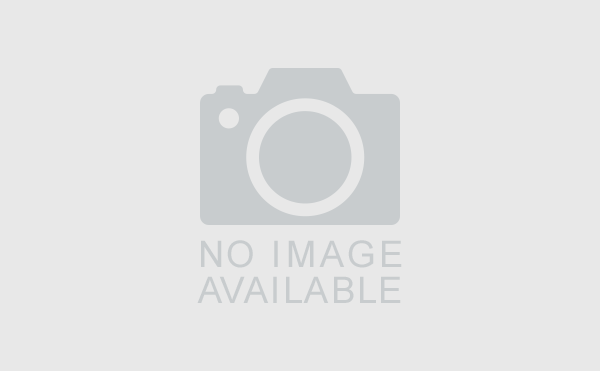保健体育第6講『衰えに立ち向かう生活習慣』
毎月第三月曜日は『保健体育』の時間です。この講座では、健康的な暮らしの営みに資する様々な知見・智慧を学びます。皆さんのセルフケアスキルを高めるための生活の知恵や最新情報を探し、お届けしていきたいと思っています。
今回は、最近、介護予防に関する講話で良く出てくる、「フレイル」や「サルコペニア」更には通称「ロコモ」と呼ばれる「ロコモティブシンドローム」について書きます。いずれも、高齢期における心身の活力が低下に関わる言葉です。始めに、この三つの言葉を簡単にご説明します。
「フレイル」は、老年医学分野で使用されている「Frailty」(フレイルティ)英語が語源になっています。厚生労働省研究班報告では「加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能)が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の虚弱性が出現した状態で「虚弱」な状態と称されています。一方で、適切な介入・支援により生活機能の維持向上が可能な状態像」と説明されています。
高齢者が増えている現代社会においては、健康な状態と介護が必要な状態との中間地点にあるフレイルに早く気づき正しく介入(治療や予防)することが大切とされています。
サルコペニアとは、加齢による筋肉量の減少および筋力の低下のことを指します。サルコペニアになると、歩く、立ち上がるなどの日常生活の基本的な動作に影響が生じ、介護が必要になったり、転倒しやすくなったりします。サルコペニアという単語は、ギリシャ語で筋肉を表す「sarco(サルコ)」と喪失を表す「penia(ぺニア)」からの造語です。日本語では「筋肉減弱症」と訳されることもあります。2016(平成28)年10月、国際疾病分類に「サルコペニア」が登録されたため、現在では疾患に位置付けられています。
サルコペニアを簡単に判断する方法として『指輪っか』方式があります。とても簡単なのでお試し下さい。

ロコモティブシンドロームとは、「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態」と定義されます。ロコモティブシンドローム(略称:ロコモ、和名:運動器症候群)という概念は2007年に日本整形外科学会により提唱されました。ロコモは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、「立つ」「歩く」といった自分一人で移動することに何かしら支障が起きている状態のことです。
加齢が進み生じる心身機能の低下に関わる三つの言葉、「フレイル」「ロコモ」「サルコペニア」の関係を概観します。『フレイル』とは、加齢に伴う予備能力の低下のため、健康な状態と要介護状態の中間として位置づけられる、心身が衰えた状態(「虚弱」)のことです。更に、こうした「虚弱」な状態から「運動機能の低下を来した状態」になることを『ロコモ』状態と言います。こうしたロコモ状態が進み、特に筋肉量の減少および筋力の低下した状態で、「筋肉減弱症」と呼ばれる疾患に分類される状態を『サルコペニア』と、言います。この関係(心身能力低下の進行)を模式図化したものが以下になります。

今回は、この三つの内で特に加齢に伴う心身の活力低下に抗う為の始めの入り口の所にある『フレイル』について、少しだけ詳しく見ていきましょう。フレイル(虚弱状態)は、正しく介入すれば防げる状態と言われているので、普段から気をつければ健康寿命を延伸できます。知っていて損はないように思いますし、何より社会的コストを下げることが出来るので、その様な意味では、フレイル予防は社会貢献につながると思います。
フレイルの判定には、日本語版フレイル基準(日本版CHS基準)というのがあります。
①体重減少:意図しない年間4.5kgまたは5%以上の体重減少 ②疲れやすい:何をするのも面倒だと週に3-4日以上感じる ③歩行速度の低下 ④四握力の低下 ⑤五身体活動量の低下という5項目です。3項目以上該当するとフレイル、1または2項目だけの場合にはフレイルの前段階であるプレフレイルと判断します。

フレイルには、体重減少や筋力低下などの身体的な変化だけでなく、気力の低下などの精神的な変化や社会的なものも含まれます。私が、フレイルを取り上げた理由は、ここにあります。即ち、フレイル(『虚弱』な状態)というのは、身体の変化だけでは無く、精神的・社会的低下も含まれていると言うことです。別の言い方をすれば、精神的・社会的状況を意識し取り組むことでも対策や予防は可能だと言うことです。この様なことに着目していたら、この考えにうってつけの本を見つけました。

『東大が調べてわかった衰えない人の生活習慣』(2018年(株)KADOKAWA)です。そこには、こう書いてありました。「社会性のあるなしがフレイル予防の大きな分岐点」と。その心は、というところを読み解いてみます。
始めに、『運動神話は絶対ではない。好きこそ健康長寿の秘訣』と、あります。様々な症例を下に導き出されたフレイル予防は、「無理して運動しなくとも、健康で長生きできる可能性は十分にある」。栄養と社会参加が鍵だと書かれています。運動が苦手だ、毎朝のウオーキングは難しい。ましてやスポーツジムに通うなどもってのほか等々の方には朗報です。
社会関係は乏しい(他者との関わりが少ない)ことを「ソーシャル・フレイル」(社会的フレイル)といいます。この社会的フレイルの予防がフィジカル・フレイル(身体的フレイル)やコグニティブ・フレイル(認知的フレイル)の予防につながり、様々な面が底上げされ、衰えない生活習慣ができあがっていくのだと説明されています。
フレイルになりたくなければ、出来るだけ「孤食」を減らすとあります。たとえ一例暮らしであっても、時々は友人と食事をするなどに意識するという物です。友達や家族とコミュニケーションを取りながら食事する共食は、栄養バランスの良い食事をとるのと同じくらい健康長寿に良い影響を及ぼします。この様なデータがあります。一人暮らしで孤食している人は、うつ傾向・低栄養共にリスクが1.5倍アップする。それよりも問題なのは、家族と一緒に住んでいるのに孤食の人は、うつ傾向が4.1倍、低栄養は1.6倍にアップし、フレイルになるリスクが増大しているのです。即ち「ソーシャル・フレイル」(社会的フレイル)状態にならないようにすることが極めて大切だと言うことです。
孤食か共食かは、ほんの一例に過ぎません。大切なことは、社会関係を適度に保ちながら暮らすこと、即ち「ソーシャル・フレイル」(社会的フレイル)状態に陥らない様にすることです。地域で行われている様々な行事やお友達同士とお茶をする等々、さほどの努力を要せずに「ソーシャル・フレイル」(社会的フレイル)予防は可能となり、そのことが始まりとなって、様々な面が底上げされ、衰えない生活習慣ができあがっていくのです。
このことを端的に表す言葉として『フレイルドミノ』があります。社会とのつながりの低下が最終的には身体の身体機能低下につながるというものです。社会参加は、栄養(食・口腔ケア)、運動とともに「健康長寿の三本柱」の重要な一本で重要な始めの一歩です。この三つの柱が三位一体となってこそ、衰え知らずの生活習慣をつくれ、『フレイル』(虚弱状態)を予防できます。

社会との関わりを持つというのは、お金もかからないし、楽しいし、健康づくりにもなる。身近な地域社会にある様々な機会に、チョット足を運んでみては如何でしょうか。このことは、ご本人だけでは無く地域社会の健全化にも寄与します。楽しむことが社会貢献にもなる!歳を重ねても社会貢献に参加できます。是非ともお試し下さい。
チョット、先週は走り回りすぎて、毎週月曜日7時の投稿アップが間に合いませんでした。申し訳ないです。ご勘弁を!