民生委員児童委員試論』第5講『3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと』
民生委員児童委員の主な活動(制度で規定している内容)は、民生委員法第14条では次のように規定されています(児童委員としての活動も対象舎が違うだけでほぼ同じなので割愛)。
1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
『民生委員児童委員試論』第5講では、第3号を取り上げます。
この項目において、多くの民生委員児童委員が行っている活動内容は、大きく二つあります。其の一は、行政から新たな支援制度が打ち出され、「対象者が困っているときには相談に乗って下さい」と、いわれて対応する内容です。例えば、低所得者への給付金制度が打ち出された場合などに良くこの様なことを行政から言われます。
其の二は、介護保険制度に関わるような内容です。急に介護が必要になり途方に暮れているようなときに、様々な制度があることを助言する場面です。この場合、民生委員児童委員自身が介護保険制度を熟知しているとは限らないので地域包括支援センターに相談するように助言することが多いように思います。
この様に、「3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
」は、新たな行政サービスが対象者に行き渡るようにする活動。そして、対象者からの相談や近隣の方からの情報で対象者の自宅に出向き必要な情報提供や助言を行うという、この二つで日常活動の大半を占めるように思います。
次に、この第3号に対しては、どのように対応しているかを書きます。この「福祉サービスを適切に使う」という内容は、多くの場合、何らかの福祉サービスを必要とする事態に陥ったときの情報提供や助言を想定しているように感じています。しかし、この事後対応では不十分なのではないかと思っています。そして、事後対応だと、社会的コストが高くなってしまいます。本人及び制度負担を最少に留めるようにしなければいけないのではないかと考えているのです。
私たち民生委員児童委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣が委嘱した、その仕事をしている時のみの非常勤特別職地方公務員です(地方公務員法第3条第3項)。この為、私たちは地方恐々団体、私の場合は仙台市の職員ということになります。この為、次の条項も適用されます。
地方自治法第2条第14項では次に様に規定されています。「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」報酬(給与)は出ませんが、この規定にあるように、「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」のです。
制度的にはこの様になっていると理解しているのですが、この様に堅く考えなくとも良く、私は出来るだけ『社会的コスト』を下げ、当事者の自律(自立)を支える活動を意識しています。この為に常に意識しているのが『予防福祉』です。
予防医学では、一次予防、二次予防そして三次予防がうたわれています。一次予防は、生活習慣や生活環境の改善、健康教育などによって健康増進を図り、『病気の発生を防ぐ』ことをいいます。適度な運動、バランスの取れた食事、禁煙・禁酒、適性体重を目指す等々が挙げられます。二次予防は、発生している健康異常を検診などによって早期発見し、早期治療や保健指導などの対策をおこなうことで、病気や障害の『重症化を予防する』ことをいいます。三次予防は、すでに病気がある程度進行し、その治療の過程や治療後においてリハビリテーションや保健指導、再発防止をとることで、『社会復帰できる機能を回復させる』ことをいいます。
これらのことは、皆さん既にご承知のことと思います。厚生労働省は、こうした一次から三次までの予防に対して『0次予防』を提唱しています。0次予防は、個人単位ではなく地域という広い範囲で対応しようという考え方です。地域を対象にして、そもそも病気や健康のことを考えなくても、『自然と健康的な行動や生活習慣ができるように、地域や社会を整える』という考え方です。
私が考える『予防福祉』は、この0次予防と一次予防をミックスしたような感じで、良く0.5次予防等と言われているものと同じ感じになります。社会との関わりの中で生活習慣や生活環境を整え、健康的な生活を主体的に送れるように、様々な情報提や助言を送りたいと思っているのです。
私にとって「福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供」とは、二次予防的な情報提供ではなく、その様な状態に至らないように一次予防に関する情報提供や0次予防となるような地域社会との関わりを支える活動に視点を置いているのです。なので、0次予防と一次予防の間にねらいを定めた活動を意識しています。
この為、多くの人と楽しく運動する活動が習慣化するような支援。現在、自主的に対応をしている方々に珈琲を提供して楽しく健康づくりが行われ、その場が人人との関わり(コミュニケーション)が密になるように様々な仕掛けを組み込むことをやっています。
また、民生委員児童委員新聞をつうじて、「早朝のウオーキングは幸せホルモンの分泌を促すのでお勧めです」等といった情報提供を行っています。また、歩くことで脳が最適化する等と言った情報を最新研究を引用して行っています。また、「おばあちゃん仮説・おじいちゃん仮説」等を紹介して、高齢者の存在の有用性を説明し、役割獲得の大切さや社会的有用感を持って頂けるようにしています。
この為、介護サービス関する情報提供は、二次予防的な情報提供なので、ここからの出発は出来るだけ少なくなるように考えています。また、その役割は地域包括支援センターの所管なので、そこにつなぐことで民生委員児童委員の役割はおおかた済むのではないかと思っています。
これらは、ほんの一例です。私が、行いたい情提供や助言は、出来るだけ介護状態に至らないようにする為の日常的な過ごし方や視点・向き合い方に関した情報提供・助言に心がけているということです。キット、このことは生きがいを持って自己実現に向けた過ごし方につながるのではないかと考えているのです。私の考える介護予防は「社会貢献」をとおして、ポジティブに行われることが大事ではないかと考えています。ダンベル体操も良いのですが、それ以上に何らかの社会的役割を担い、楽しく生きがいのある活気に満ちた生活を送ることが、結果として介護予防につながるのではないかと考えるのです。
私にとっては、こうした情報提供や助言が、「3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと」だと思ってやっています。

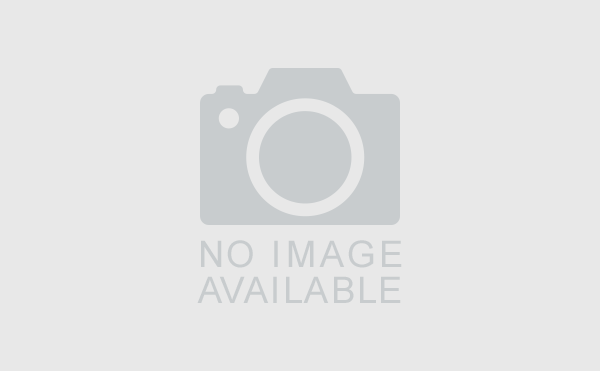
一次予防,二次予防,三次予防の話,「そうだ,そうだ」と久しぶりに自分の仕事を振り返りながら読ませていただきました。
民生委員と聴くと,「困ったことがあった時の相談相手」が私の一番のイメージで,今も変わりません。なので,活動内容もどちらかと言うと主な活動の2,3が浮かんできます。
確かにそれらは,民生委員としての大切な役割,活動だと思います。
それが今回の私論では,3の活動について,『私にとって「福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供」とは、二次予防的な情報提供ではなく、その様な状態に至らないように一次予防に関する情報提供や0次予防となるような地域社会との関わりを支える活動に視点を置いているのです。なので、0次予防と一次予防の間にねらいを定めた活動を意識しています。』と,具体的な活動と共に書かれていました。
健康づくりでは,その人一人ひとりの状況から,1次予防(生活習慣などに気をつけて病気にならない),二次予防(早期発見・早期治療で悪化を防ぐ),三次予防(社会復帰していく)のどれもが大切なことです。そして0次予防とは,個人の努力に依存せず,生活環境や地域社会の基盤の整備をすることで,健康的な行動や生活ができていくという考えだと思いますが,それら0次~1次を意識した活動により,『予防福祉』につながっていったらいいねということですね。
そのきっかけは気づかないだけで,実は私たちの身の回りの地域の中にたくさんあるのかもしれません。目的の目的を考えると目標が見え,手段も浮かんでくると思います。
継続していくことは大変だったり,いろいろな苦労もあると思いますが,みなさんの笑顔や楽しいと言う気持ちが支えになり,地域の中での『予防福祉』の機運が高まっていったらいいですね。
民生委員の活動では、個別の心配事や生活課題に注目して、どこに相談すればそれが解決に向かうのかの繋ぎ役をしてくれるのですね。
まずは困りごとをひとりで抱え込まないように、地域との関係性が良きものである必要があります。それが転ばぬ先の杖となるとみんなが理解しておけると良いですね。
例えば認知機能が低下してきた家族がいる時、その人ひとりに手を差し伸べても不十分です。家族全員がどのように理解して、どこまでなら家族でケア出来るのか、それ以上は誰にお願い出来るのかということまで道筋が立たないと安心して暮らせませんね。
また、ひとつの事例がこれで上手く繋げたとして次もまたこの通りとはいかず、十把一絡げの対応では個別の事情にはマッチしにくいことでしょう。
こうして考えると民生委員には人生経験と地域愛が不可欠のようです。その上で行政や制度への理解と協力の姿勢も求められている。
なんと尊いお役目、ご苦労さまなことです。
私もこれからは地域の話題や課題など、気がついたら民生委員さんにお話するようにします。
その仕事内容もわからずにお世話になっている方々が、まだ他にもたくさんあります。ひとつ知れば感謝の気持ちが湧いてより良い関係性が作れると思います。
為になるお話をありがとうございました。