かじってみよう社会学Ⅱ第5講『地域活動を社会学の視点で見ると!』
第1月曜日は講座名 『かじってみよう社会学Ⅱ』です。生活に役立つ「地域社会と利他」を主テーマに、社会学の視点から日々の生活や地域社会での出来事を考えてみたいと思っています。
第5講目の今日は、『地域活動を社会学の視点で見ると!』と題して、地域社会で行われて活動に内包されている様々な事柄を社会学の視点で少しだけ掘り下げてみます。こうした試みにより、皆様が行っている諸活動の持つ役割がより明確に見えてくるのでは無いかと思います。
様々な活動は、個人又は団体で行われますが、今回は団体で行われる活動を下にして考えてみます。ここでは、私も関わっている「晩酌の会」と「ラジオ体操に参加する人々」を事例にして考えてみます。
毎朝、長命ヶ丘南緑公園では、20人ほどの近隣住民が任意で集まり、朝6時30分からのNHKラジオ体操をしています。その場所に、月1回の頻度で「晩酌の会」のみなさんが『おせっかいCafe』を開店し、チョットして交流の場を設けています。ラジオ体操だけの時は、体操が終わると同時に解散しています。月一回の『おせっかいCafe』の時は、みなさんお漬け物や野菜(先日はトマト)等々を持ち寄り、30分程の時間を珈琲を飲みながら世間話をしています。
『おせっかいCafe』のあるときと無いときの差は歴然としています。あるときは、滞在時間が長くなり、漬け物や野菜、旅行に行ってきたからと旅行先のお土産が所狭しと並びます。「晩酌の会」が用意しているのは、珈琲と手作りの焼き菓子だけです。会話の量は、全く異なります。10年以上この場所で体操を行っている方は、この違いに驚いています。
概要はこのくらいにして、始めに、この集まり、即ち「集団」について考えてみます。この集団(社会集団)は、任意の参加、口コミで知っての参加で不特定多数の方々が参加しています。不特定多数といっても、出入りは少なく、多くは顔なじみになるほどの固定した人々に、口コミで知った新たな参加者がポツポツと増えている状況です。最近では、犬の散歩の方が立ち寄ってくれるようにもなっています。この集まりはこの様な感じの集まりです。
2年前の復習になりますが、社会集団は、社会学者によって類型化されていますが、各学者により名称や類型化する際の基準が違っています。ここでは、一般的に分かりやすい四人の学者の類型で説明します。
クーリー(接触の様態)
・第一次集団:体面的な直接的接触による親密な結合と協力を特色とする。家族や遊び仲間等
・第二次集団:間接的接触に基づいて目的意識別に形成される。国家、政党、労働組合等
テンニース(結合の性質)
・ゲマインシャフト:感情的融合と特徴とし、愛情、了解といった人間にとって本質的なものを表す本質意志に基づいた、全人格的な結合(共同社会)
・ゲゼルシャフト:人為的、作為的に形成される形成意思(選択意志)に基づく、打算的でインパーソナルな結合の(利益社会)
マッキーバー(関心の充足度)
・コミュニティ:一定の地域で営まれている自主的な共同生活。全体的な関心を共有する。
・アソシエーション:コミュニティを基盤として、ある特定の関心(部分的関心)を追求し、特定の目的を実現する為に人為的に形成された集団。
みなさん、だいぶ前になりますが記憶を呼び戻してみて下さい。何となくですが、耳に聞き覚えがあるかと思います。クーリーの第一次集団は、「四国八十八ヶ寺歩きお遍路」でも触れているので、多分、一番始めに思い出せたのではないかと思います。
では、この四人の学者の説で、ラジオ体操場面を説明すると、どうなるでしょうか。一番しっくりくるのは、マッキーバー(関心の充足度)「アソシエーション:コミュニティを基盤として、ある特定の関心(部分的関心)を追求し、特定の目的を実現する為に人為的に形成された集団」と、いったとこでしょうか。どちらこと言えば合っていそうなのは、クーリーで言えば「第二次集団」。テンニースで言えば「ゲゼルシャフト」。この様な感じになるかと思います。この様に、私たちが関わる又は創った集団は、何らかに分類することが出来ます。この為、その分類に合った意図・運営を意識して活動を行うとより誤解の少ない効果的な運営が出来るようになるかも知れません。
次に活動の様子から学び取れることを書いてみます。
NHKラジオ体操に参加している人たちは、一様に楽しそうです。晩酌の会のメンバーは、体操の終わる時間に合わせて珈琲を淹れ始めています。何が面白いのか分かりませんが、珈琲を片手にお漬け物を食べ会話が弾んでいます。お漬け物を持ってきた人は、問われるままにその作り方やコツを説明しています。男性の方は、自宅から模型を持ってきて、お漬け物に並ぶテーブルに置き「講釈」しています。珈琲のお代わりをすすめる晩酌の会のメンバーは「美味しいです」と奥様方に言われて照れています。子ども(小学校5年生)は、遠巻きにしている方々に珈琲を持って駆け寄り「おはようございます、珈琲です」と、手渡ししています。
これの様子からは、「楽しい」「居場所」「役割」「社会化過程」「健康寿命」「貢献寿命」「サードプレイス(義務や責任から解放され、リラックスして自分らしく過ごせる場所であり、心の安らぎや新たな活力を生み出す場所)」「大人の嗜みとしての遊び」等々のキーワードが浮かんで来ます。
最近よく聴く「居場所」は、不登校に関する議論でよく出てきます。しかし、高齢者の引きこもりに関する議論でも良くテーマになります。居場所は、社会学のみならず、社会心理学や発達心理学観点の観点でも取り上げられます。私が考える居場所は「いても良い場所・心が安らぐ場所」から「必要とされる場所・新たな活力を生み出す場所」という視点での見方・取り組み姿勢いといったものになります。即ち、「居場所」は、役割獲得の場としても機能し、其れを下にして自分らしさや自己肯定感の向上等が期待されると考えるのです。
次に「楽しい」はどうでしょうか。楽しさとは、一般的には、何かをすることや見ることや聞くことなどによって、心が満たされたり、喜んだり、興奮したりする感情のことを指します。心がワクワクして笑顔になり、身体中にエネルギーが満ちるような感覚を「楽しい」と捉えることが多いようです。「楽しい」には様々な感じ方があり、その意味合いも人によって異なり多面性を持ちます。この楽しいを二つに分けて考えてみます。
其の一「情的な楽しさ」は、高揚感や刺激を伴う「快」の状態を指します。心地よく、気分が高まるような楽しさで、旅行での豪華な食事などが例として挙げられます。一方、情的楽しさの持続性は比較的弱いとされます。
其の二「意的な楽しさ」は、必ずしも楽ではないし負荷も伴いますが、深い部分で喜びを感じる「泰」(たい:やすらか / おだやか / 落おち着ついている)の状態です。活力や自信、使命感につながり、持続性があります。発展途上国での医療活動やそこまででなくても、身近な近隣での社会貢献などがこれにあたります。
楽しいと感じることは、日々のストレスを軽減し、精神的な健康を保つことにつながります。自分の好きなことや没頭できる趣味を持つことで、ストレスが減少し、心身の健康を維持しやすくなります。楽しいことに積極的に取り組んだり、他者に感謝されたり喜ばれたりすると、自己肯定感(自分は価値のある存在だという感覚)が高まります。この自己肯定感は、人間関係やキャリアなど、人生のさまざまな側面に良い影響を与えると言われています。
更には、楽しいという感情は、何かを学ぶ意欲や目標達成へのモチベーションを高めます。また、楽しいと感じている時は、新しいアイデアが生まれたり、問題解決への創造性が発揮されやすくなります。「人生は楽しむためにある」という考え方は、新しいことに挑戦する意欲を引き出します。楽しいことを見つけ、積極的に行動することで、人生はより豊かになります。先入観にとらわれず、素直な気持ちで新しいことを試してみると、思わぬ楽しさや出会いが広がることもあります。
きっと、食べたり飲んだりしているだけではなく、そこで感じる「楽しい」という感情は、様々なポジティブな感情が湧き出るように生まれてくる場となっているのではないかと思います。
三つ目は、「社会化過程」です。小学校5年生が、大人に混じって珈琲を配っています。そこでは、大きな声で挨拶をしたり、頭を下げたり、何らかの受け答えもしています。彼は、大人との社会関係の中で、様々基本的な振る舞いの仕方を学んでいるように思います。即ち、一次社会化過程の中にいると考えています。一次社会化は、幼児期から、児童期にかけて行われ、言語や、基本的な生活習慣を習得する機会です。この時期に社会化された事柄は、その後の学習の基本になります。また、一次社会化の担い手は、主として家族です。しかし、この体操の場は地域の大人です。家族単位であらゆることが済まされる現代社会において、家族だけではなく地域の大人も一次社会化に関わることはとても大切なのではないかと思っています。
役割やサードプレイスは、これまでの記述の中で読み込めると思うので省略します。これまでみてきたようにNHKラジオ体操とおせっかいCafeのコラボで生まれた空間(場)は、様々な機能を内包した空間として存在しています。こうした住民の居場所がさり気なく存在する地域社会は、今後益々必要になるものと考えています。
また、現在、活動を行っている皆さんは、自分が行っていることをことさらに自己主張する必要はありませんが、こうした役割や意味を持っています。心ある方は、きっと分かっていると思いますので、大変だろうとは思いますが、「楽しい」を忘れずやり続けて下さい。











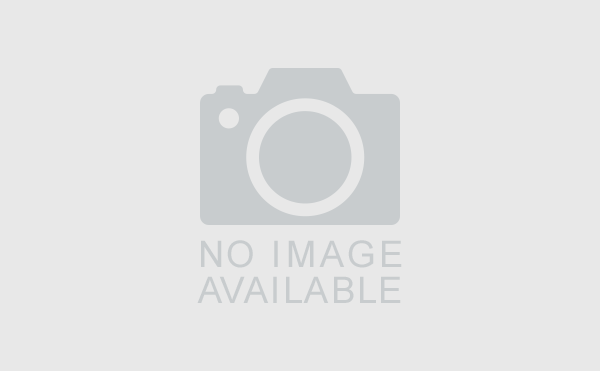
L.Kさん コメント有り難うございました。コメントという『お布施』を頂きよろこんでいます。「おおくの差し入れ」、その通りなんです。毎月、みなさん「お漬け物」「旅行帰りのお土産」等々を手にして差し入れして下さいます。私が、始めの頃にその様子をみたとき感じたのは、少し前まで地域社会ではこの様な様子があったなっていうことでした。地域のお茶会は、みなさん一皿持ち寄りでお茶おしゃべりを楽しんでいました。その時、思ったのです。この様な「場」をつくれば、みなさんのこれまでの振る舞いを思いだし、求められるのではなくて自ら、この様な指し入れを持ち寄るようになると。そう考えると、私たち「晩酌の会」の珈琲提供は、コミュニケーションツールであると同時に「場づくり」のツールにもなるのだと学ばせてもらいました。ここに集まるみなさんの関係性も深まり、そして広がって行くことを楽しみにしています。実は、良く街中でみる縦に長い旗を作ったんです。機会を設けてご紹介します。この度は、コメントを有り難うございました。
写真を大きくして見ていたら、3枚目の写真にびっくり!すごい量の差し入れですね。
月に一度のおせっかいカフェを楽しみにしていること、居場所になっていること、それも「何らかの役割を持って」みなさんが参加していることなどが伝わってきます。
ラジオ体操で団地の広場にみなさんが集まってくるというのは時々聞きますが、終われば言葉も交わさずにお帰りになる方もいらっしゃることでしょう。それが、月に一度でもこのような場があると言うことは、お散歩中の人も立ち止まって温かいコーヒーをいただきながら、普段できないおしゃべりやご近所さんを知ることができるとても良い時間になると思います。