保健体育第4講『お薬手帳を持ちましょう』
毎週第3月曜日は保健体育です。健康的な暮らしの営みに資する様々な知見・智慧を学びます。皆さんのセルフケアスキルを高めるための生活の知恵や最新情報を探し、お届けしていきたいと思っています。
今回は、私自身の失敗談を下にしてお話しをします。実は、8月の下旬にチョットした皮膚に気になることがあり切除してもらい、その際、「抗生物質」と「痛み止め」を処方されました。当日から服用したのですが、翌日から指や身体のあちこちがかゆくなり発疹が出てきて、日を増すにつれてひどく腫れて来ました。薬の服用は直ぐに止めたのですが、発疹、かゆみは増すばかり。40代の頃にパラグライダーで墜落して入院し、その際に処方された痛み止めで、粘膜が腫れ大変な状態になった時に近い症状になったのです。
数日我慢していたのですが、腫れた指に水疱が出来てしまい、これは「薬疹」ではないかと、皮膚科を受診しました。受診時には、これまでの服薬の経過を聞かれたのですが、お薬手帳もなく記憶もあいまいでした。さいわい、マイナンバーカードの保険証を紐付けしていたので、これまでの処方実績は読み取ることができました。ただ、どれが原因かは分からず、入院して調べないと特定は出来ないとのことでした。いずれ、いずれ服薬した抗生剤と痛み止めは、黒として記録しておくように助言されました。
この上で、かゆみを感化する薬と炎症を抑える塗り薬を処方され、現在の治療中です。ここまでで3週間です。症状は、少しずつ緩和していますが、まだまだ完治には至っていません。これまで、「ボルタレン」という痛み止めはダメだと知っているので、それは避けていたのですが、違う痛み止め又は抗生剤で薬疹が出てしまいました。今後も、何があるか分からないので、いつかは入院して、身体に合わない薬(成分)を特定してもらおうと思っています。
この様なことはあったので、この際、「薬疹」について調べてみて、皆様にも「薬疹」について知ってもらい、「お薬手帳」の活用をお勧めしたいと思います。
薬疹とは、薬を内服したり注射したりすることにより生ずる発疹のことです。その中でも問題となるのは、薬を投与されたごく一部の人に生ずるアレルギー性薬疹です。ふつう薬疹といった場合には、このアレルギー性薬疹を指し、薬に対して反応するような細胞や抗体がある人(これは、薬に感作された状態と呼びます)にのみ生じます。通常、薬に反応するこのような細胞や抗体が出来るのには内服を始めて1~2週間程かかるので、そこで初めて発症すると考えられています。ですから全て内服したことのない薬で(アレルギー性)薬疹を生ずることはないはずです。もし、あったとすれば、それは既にその薬と似た構造を持つ他の薬に感作されていたと考えるべきでしょう(日本皮膚科学会)。
薬疹は、次のような症状が現れます。発疹、小さなプツプツ、皮膚のかゆみ、発熱、のどの違和感、
のどの痛み。です。
アレルギー性薬疹の場合、その薬に対するアレルギー反応は一生続くと考えて良いと思います。ある薬で薬疹を起こしたら、その薬はもう一生内服出来ないと考えて良い。この為、一度アレルギーを起こした薬の名前は、薬を処方される度に必ず提示して、避けてもらう必要があります。この時、とても有効なのが『お薬手帳』です。
薬疹の種類・分類は、以下のようになっています。
・多型紅斑型 円形の紅斑が現れます。同心円状に拡大し、二重丸や三重丸のように見えることもあります。抗生剤、痛み止めの使用で起こりやすいタイプです。
・播種性紅斑丘疹型 薬疹のうち、もっとも頻度が高くなります。全身に紅斑(持続的な皮膚の赤み)、丘疹(皮膚から盛り上がった発疹)が現れます。抗生剤を含め、さまざまな薬の使用によって起こります。
・水疱型 全身に水疱やびらんが生じます。 糖尿病治療で用いられるDPP-4阻害薬が原因になることが多くなります。
・蕁麻疹型 唇の腫れに加え、息苦しさや呼吸困難の症状が現れることがあります。呼吸器の症状が出ている場合には、救急外来の受診も検討します。さまざまな薬の使用によって起こります。
・扁平苔癬型 主に降圧剤を原因としますが、服用開始後半年~数年して皮疹が出現するため、薬疹と結びつけられないこともあります。
・湿疹型 接触性皮膚炎(いわゆる「かぶれ」)のような多彩な皮疹、かゆみを伴います。
・固定薬疹型 同じ部位に繰り返し皮疹が現れ、回数を重ねるごとに症状が悪化していきます。解熱剤、風邪薬を原因とすることが多くなります。
・光線過敏型 薬を使用後、日光を浴びることで、皮疹が出現します。高血圧や脂質異常症の薬、便秘薬、湿布薬などが主な原因となります。
・ざ瘡型 副腎皮質ホルモンやビタミンB12などを原因とすることが多くなります。
・粘膜型 主に、痛み止めの使用を原因として起こります。
・重症型薬疹 主に、痛み止めの使用を原因として起こります。
薬疹になったときは、その薬を処方した医師に相談する(私はしないで別の皮膚科に行ってしまいました)。抗がん剤に代表されるように、薬の使用を中止すべきでないケースも存在します。中止を検討すべきと判断された場合には、皮膚科の受診をおすすめします。皮膚科を受診する際には、お薬手帳、原因と考えられる薬を持参することが勧められています(出典:hp富田るり子皮膚科クリニック)。
薬疹はさまざまな薬によって引き起こされますが、中でも頻度が高いものとして、アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの鎮痛剤、カルボシステインなどの去痰剤、クラビットやジェニナックなどの抗菌薬が挙げられます。私が、薬疹ないかと思ったときに処方(8月29日)されていた薬は、痛み止め『アセトアミノフェン錠200mg』(主成分:アセトアミノフェン)。抗生剤レボフロキサシン錠500mg(主成分:レボフロキサシン水和物)。後で、よく調べてみたら、二つとも副作用のリスクがあると書いてありました。鎮痛剤がドンピシャ大当たりでした。
また、その前(7月25日)に風邪の症状で受診したときに処方されていたのが、抗生剤クラビット錠250mg(主成分:レボフロキサシン水和物)及び痛み止めカロナール錠200(主成分:アセトアミノフェン)
薬疹は、内服から1~2週間で発症するとあります。なので、8月29日に外科で処方された痛み止めを服用して翌日には発症したのは、医学的見地からはおかしいことになります。しかし、直近の服用歴を調べてみたら、その服用の薬1ヶ月前に、同様の成分(アセトアミノフェン)を主成分とする痛み止めを服用していたのです。よくよく、思い出すと、今回の指の部分や身体に、かゆみと腫れを感じていたのです。その時は、虫にでも刺されたのかと思い放置していたのです。その内に、収まっていたので記憶から遠のいていました。
今回、「薬疹かも!」と思えたのは、異常なかゆみや皮疹が一ヶ月前と同じ場所だったからです。今回、改めて「薬疹」について調べてみたら、「内服したことのない薬で(アレルギー性)薬疹を生ずることはないはずです。もし、あったとすれば、それは既にその薬と似た構造を持つ他の薬に感作されていた(薬に対して反応するような細胞や抗体が出来ていた)と考えるべきでしょう(日本皮膚科学会)」とありました。即ち、私の場合、1ヶ月前の痛み止めの処方で「薬に対して反応するような細胞や抗体が出来ていた」ところに、再度、おなじ成分を持つ薬を処方され、一晩で薬疹の症状が出てしまったようです。
なので、1回目の異常なかゆみや腫れの段階で気がつけば、1ヶ月後の処方の際、申し出て今回のひどい薬疹は防止出来たのだと思います。なので、お薬手帳で成分等をチョットでも見ておけば、何とかなったのではないかと、今さらですが思っています。
薬手帳を持参すると医療費が少し易くなります。薬局で薬を調剤してもらう際には、「薬剤服用歴管理指導料」が発生します。2016年4月の診療報酬改定により、薬手帳を持参すると管理指導料は380円で、持参しなかった場合は500円がかかることになりました。持参した場合としなかった場合の差額は120円となり、医療費の自己負担が1割の人は10円、3割の人は40円の差額が生じる計算です。
但し、薬手帳を持参して医療費が値下がりになるのは、「6カ月以内に同じ薬局で薬を処方してもらったとき」のみです。6カ月以上薬局に行かなかったときや、別の薬局で薬を処方してもらった場合は薬手帳を持参しても安くなりません。また医療機関の近くにあり、主にその医療機関の処方箋を扱っている「門前薬局」で処方してもらう場合も安くならないため、注意が必要です。
以上、私自身の体験から「薬疹」について、そしてその体験から「お薬手帳」の大切さについて書きました。携帯電話などにも「お薬手帳アプリ」を入れて管理できますが、やはり紙ベースのお薬手帳が、色々とメモしたり簡単に振り返られる等、利便性を超えた使い勝手があるように思います。この機会に、是非開いて見てその様な薬・成分を摂取しているのかを確認してもよろしいのではないかと思います。
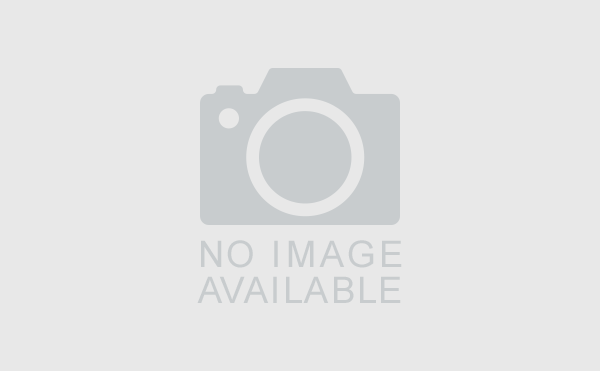
少しずつ症状が緩和されているとのことですが,その後,症状はいかがでしょうか?
読んでいて,なるほど・・と勉強になりました。
コロナのワクチン接種の問診にありましたが,アナフィラキシーショックのことも頭をよぎりました。
実は私も薬疹が出たことがあります。
先生が何種類かの種類を書いてくださいましたが,私はもっとも頻度が高いという「播種性紅斑丘疹型」だったかと思われます。ある抗生剤の点滴を受けたあと自宅に戻り,膝小僧が無性に痒くなり,丘疹(皮膚から盛り上がった発疹)が現れました。そのときは,その抗生剤が原因かどうかは半信半疑でしたが,それから数年経って,それと同じ飲み薬を服用したときに同じ症状が出たので,「これだ!」と確信しました。
それからは,歯科の抜歯を始め,抗生剤を使用するときや予防接種の問診票には必ず記入するようにしています。幸い,それ以外の抗生物質は特に症状が出ていません。
お薬手帳,大切ですよね。
こちらの住民さんで,医療機関ごとにお薬手帳を作ってらっしゃる方がおりましたが,それだと手帳の意味が半減してしまうので,1冊にまとめることをお薦めしたことがあります。
あと先生のような症状が出た場合の薬は赤で囲って×でも記し,新しい手帳になった場合はその部分をコピーして挟めておくことが必要になるかと思います。
それにしても,本間先生の場合,「抗生物質」よりも使用頻度が多いと思われる「痛み止め」で大変な症状が出るようなので,早めに身体に合わないもの,合うものを調べてもらっておいたほうが良いと思います。
ですよね(^^;)?!