かじってみよう社会学Ⅱ「席を譲るあれこれ」
公園でラジオ体操や犬の散歩をしている人に、珈琲を無償で提供している団体があります。今回は、夏休み中と言うことも有り、小学生3人がお手伝いに加わり、通りかかる人たちに珈琲を持って駆け寄りお渡しをしていました。そんな中、犬を連れて散歩中の高齢者に、珈琲と作りクッキーをお持ちしたところ「ご飯食べてきたからいらない」と、お断りされ受け取ってもらえす、小学生がうな垂れて戻ってきました。それを見て何かスッキリしない私がいます。電車やバスの中でも同様に、高齢者を見て席を立った中学生に「大丈夫だから」等々といって、そのまま立っていて、中学生がばつが悪そうにしている様子を見たこともあります。
今回の『かじってみよう社会学Ⅱ』は、この様子をどのように理解すれば良いのか様々考えてみたのです。
始めに昨今のSNSに投稿された内容を拾ってみます。
質問:お年寄りに席譲るのは大事だけど、老けて見えるのってキレる人いるだろうし難しくないでしょうか?
回答:別に難しくないですというより難しく考えて「だから譲りたくない」と考えてしまうことの方が好ましくありません。こういう話があると「せっかく譲ってやっているのに固辞された。自分が恥をかいた。譲られたら座りたくなくても我慢して座れ。高齢者に席を譲ってやった自分は周りから評価されるべきだ。何故感謝や尊敬を向けないんだ」みたいな考え方をする人がいます。そして「だから席を譲る気がしない」と考えてしまうわけです。高齢者は「席を譲る側の自己満足を満たすために若い人に気を遣わなければならない存在」ではありません。
また、同様の趣旨にたいする回答には「電車の席譲るときに『どうぞ』という奴は偽善者じゃないの?自分はもうすぐ降りるから、みたいな雰囲気を醸し出して黙って席を立てばいいだけのことなのに。残念ながら、人前でどうぞといって席を譲る光景って現実にはかなり違和感ある(ID非開示さん)」。
更に「確かに妊婦とか身体障害者、病気の人など弱者のための優先席はいいが、年寄りというだけの理由で座れるような優先席は要らないのではないかと思う。気の弱い老人や年寄りは、座席を譲られると座らないと申し訳ないと思って座ってしまうかもしれないが、そこは同調圧力に負けてはいけない」。
この様な記事もあります。「高齢だから、という理由だけで優先席は要らない。50歳を過ぎたら、本当に座らなければならないほど苦しくなったときに備え、原則、電車やバスの席に座るべきではない。座らない癖をつけよ。それが自分のため、それが体力づくりのためだ。そして、自分が座っている前に若者が、なにやら疲れた様子で不機嫌そうに立ったら、すかさず立ち上がって席を譲ろうではないか。立ち上がって、次のように言うのだ。「どうぞ、お座りください。私たちがこうやって暮らしていけるのも、年金のおかげ。その年金や医療費は、あなた方のような若い人たちが一生懸命働いてくださるから。えぇえぇ、感謝してますよ。どうぞ座ってください。そして、お疲れを取って十分に働いてください」そう言って慇懃(インギン:真心がこもっていて、礼儀正しく)に話しながら座席を譲るのだ。そういう老人、年寄りが増えれば、若者は、かえって老人に敬意をもつようになるだろう(一般財団法人東アジア情勢研究会理事長江口克彦)」。
また、高齢者には「座ってしまうと立ち上がるのが難しく、座席からドアに移動するのもかえって危険だから」というのが理由も少なくないと言います。ひざや股関節、それに腰椎の変形が進んだ場合、立ち上がる動作そのものに痛みが伴う。痛みがなくても、加齢による筋力低下で、立ち上がったり、車内を移動したりするのがつらいというお年寄りもいる。座った姿勢から立つときに重要な役割を果たす太ももは筋力低下が早く進むため、80代の男性では2割から3割ほどの人に、立ち上がるのがつらい症状があるのではないかと指摘しています。ある程度高さがあるいすなら便利なのですが、電車やバスの座席は低く、立ち続けるほうが楽なのです(国立長寿医療研究センター病院・ロコモフレイルセンター松井康素(整形外科))。
同様な視点で「いったん座ったら立ち上がりにくいので、腰かけたくないという人もいるでしょう。健康を保つため、乗り物ではできるだけ座らず、つり革などをしっかり持って筋力とバランス力のトレーニングに挑戦するよう、医師から勧められている場合もあります。また、自分は若いと思っていて、席を譲ろうと声をかけられると不愉快に思う人もいるでしょう。座らない理由はいくつもあります」(日本股関節研究振興財団理事長別府諸兄)
一方、高齢者自身の振る舞いに対する記事もあります。30代のサラリーマンという投稿者は、職場に向かう通勤電車でラッシュの時間に乗り込んでくる登山者たちに辟易し「通勤電車、基本的にお年寄りがいたら席を譲るようにしているんだけれど、明らかに『これから登山行きます』って格好の老人に関しては申し訳ないけれど譲らない。こちとらこれから地獄の労働なんだ。好きで体力使って遊びに行く人にまで座席を譲る余裕はないんよ」。投稿者の男性は、「明らかに登山に行く風貌の高齢者グループと通勤電車内で遭遇し、気のせいかもしれませんが座席を譲るようプレッシャーを受けたので、モヤモヤして投稿しました。過去にも何度か同じような経験をしています」と経緯を説明しています。
この投稿は8000件以上のリポスト、16万件もの“いいね”を集めるなど話題に。「気持ちはわかる」「元気そうな人には譲ってない」「働いている現役世代の方が疲れてる」といった声や「優先席あるんだから譲って欲しい人はそこに行けばいい」「年寄りも元気なら健康の為にも立った方がいい」「登山の人だったら譲るのは逆に失礼かと思っちゃう」という意見、「登山の格好した老人がリュックでひと座席使ってて流石に腹たった」「あー若い人は座れてて良いなぁとか嫌味たらしく言ってくる」という体験談など、さまざまな反応が寄せられている。
さらに、当然お年寄りだけではなく、妊婦さんにも席を譲るべきだとは思うが、見た目だけでは判断つかない場合がある。「万が一、違ったら失礼になる」と考える人も多い。妊娠を周囲に知らせる「マタニティーマーク」もあるものの、それを付けていることによって、逆に妊婦さんが不快な思いをする事態も発生しているという。
なかにはマタニティーマークを見て、「幸せ自慢か?」「妊婦は偉いのか?」「不妊治療をしている人の気持ちも考えろ」と思う人もいるそうだ(産経ニュース2016年1月1日付)。個人的には妊婦は偉いと思うのだが、どうだろうか。少なくとも批判の対象になるのは、どう考えてもおかしい。しかし、世の中にはいろいろな考えの人がいるものだ。ますます公共の場での振る舞い方が、難しい時代になっている(ダイヤモンド・オンライン:フリーライター宮崎智之)。
こうした様子を数値的表した調査もあります。乗り換え案内サービス「駅すぱあと」を提供するヴァル研究所が2016年11月に発表した調査結果によると、「お年寄りなど優先すべき人がいた場合は、優先席では席を譲るべき」と考えている人は75.9%で、2013年に行われた同様の調査と比較すると、約17%も減少していることがわかっている。わずか3年で激減している。
また、「優先席以外でも席を譲るべき」と考えている人は全体で57.1%いたが、こちらも2013年調査と比較して約19%も減少している。ちなみに、優先席、優先席以外ともに女性のほうが男性よりも「譲るべき」と考えていない傾向が強いという。
その一因となっているのは、やはり「譲ろうとしたが、断られた」という苦い経験だ。同調査によると、61.0%の人が席を譲ろうとして、相手に断られたことがあると回答している。つまり、半数以上の人が席を譲ろうとした経験があるにもかかわらず、なんらかの形で拒否された経験があるため、「親切にしても、相手か嫌がるなら……」と萎縮して、その後は譲るのを控えるようになったということである。ともやりきれない。また、相手がそう感じるのではないかと忖度し、声をかけるのを萎縮することによって、本当に席を譲らなければいけない人が不利益を被ることがあるのだとしたら、それは由々しき事態である。
これらは、様々な記事や投稿から抜粋したものです。必ずしも一般的な傾向を代表する意見では無いかも知れませんが、他者との関わりの中で日常的に生じる課題のように受け止めています。ここにあるような、それぞれの考えの下になっていることは、電車・バスで席を譲る、拒否するだけのことではなく、地域社会に於ける近隣関係にも現れていると考えるからです。
私たちの身近な地域社会に於ける関係性の希薄さが様々指摘されています。その際「プライバシーの保護」がその理由として挙げられることが多いように思います。しかし、今回取り上げた、席を譲ることや珈琲を受け取らないこと等々を重ねてみると、もっと別のところにも課題が潜んでいるのではないかと考えるのです。
ここでは、二つの言葉に注目して書いてみます。
其の一つ目は『忖度』(そんたく)です。国会議員と行政職員との関わりの中で何度か出てきて、印象の良くない言葉として扱われていますが、忖度の本来の意味は、「相手の気持ちを推測すること」を意味する、ポジティブな言葉です。忖度には日本人の性質があらわれています。忖度のほかに相手の気持ちを推測することを意味する言葉としては、「阿吽(あうん)の呼吸」などが挙げられます。
「忖度」「阿吽の呼吸」といった言葉には、日本人の性質があらわれています。かつては、社員に対して画一化した教育を実施する日本企業が多く、相手に「忖度」し、「阿吽の呼吸」によって業務を進めていく様子が見受けられました。社員同士が、阿吽の呼吸によって成り立つ関係であれば、上司は部下に対して細かい指示を出す必要がなく、業務を効率的に進めることが可能となります。
相手の気持ちや状況を配慮する日本人の性質が業務効率化にもつながっており、仕事においても大切な言葉だと考えられます(働き方改革ラボ20250901)。
こうした「忖度」には、『社会学的想像力』(アメリカの社会学者C. ライト・ミルズが提唱した考え方)が必要です。社会学的想像力とは、身近な出来事を広い文脈と結びつけて考える能力、またそれとは逆に、広い世界の出来事を身近な問題として考える能力のことです。誤解を恐れずに簡単に表現すれば、個人が抱える課題を、個人の問題としてだけではなく、家族関係の視点から、近隣関係との折り合いの視点から、制度の欠陥の視点から等々、様々な視点から時間軸なども加えながら課題に接近していくことです。
前述した事例は、「忖度」(相手の気持ちを推測すること)及びその下となる「社会学的想像力」が弱くなっているからなのではないかと考えるのです。相手の気持ちを様々な角度から推し量り、理解しようとする気持ちが少々弱くなり、物事を目の前にある事象でしか理解しない。あるいは、一つの事柄をことさら大きく取り上げ、その負担の大きさに尻込みをしてしまい、「いっそ、関わらない方が楽」との選択に走ってしまう。
近隣関係の希薄さを語るときに持ち出される個人情報保の件は、個人情報保護法そのことよりも、(本来の意味での)「忖度」「社会学的想像力」を妨げるものあるいは言い分けとして使われているだけで、地域社会に於ける最大の課題は「忖度」「社会学的想像力」が弱くなっているところにあるのではないでしょうか。
其の二つ目は『中庸』(ちゅうよう)です。中庸とは儒教を起源として「極端に偏らず、また過不足なく調和がとれていること」を意味します。これまた誤解を恐れず簡単に表現すれば、「バランスを取ること、偏りがないこと」即ちバランス感覚です。
この考え方が、別の形で出てしまったのが「同調圧力」です。日本人は、同調圧力に弱い傾向があります。そもそも、皆と一緒でないと浮いてしまうのではないかと不安になり、同じ行動を取る傾向があります。同調圧力とは、ある特定の同等集団(地域社会・職場など)において意思決定、合意形成を行う際に、少数意見を有する者に対して、暗黙のうちに多数意見に合わせるように誘導することを指します。別の言葉では、文筆家山本七平の「空気」、歴史学者阿部謹也の「世間体」という概念も、同調圧力に通じる考え方です。また、「出る杭は打たれる」もこれに近いかも知れません。
地域社会において、自分では必要だと思っても、周りから何を言われるか分からない、自分だけ他と違ったことをすると浮いてしまうのが不安などは、良く聴くお話しです。こうして、せっかく「社会学的想像力」で課題に気づき行動を起こそうとしても、同調圧力が近寄ってきます。前例というぬるま湯に浸かっていたが方楽だし波風も立たず淡々と行えます。個人の意志でやっている分には無視されるだけで済むのですが、こと地域社会の活動(地域力)になると、この同調圧力が手強い存在となります。前例にとらわれることなく、社会的想像力を持って地域課題に取り組もうとする人は、それほど多くはないのです。
こうした「忖度」や「中庸」といった本来日本人が持っていた他者との関わりに於ける基本的な姿勢が次第に弱くなり、「忖度」は過度に人の目を気にして多くを語らないようになります。また「中庸」で言うバランス感覚は、波風立てないという形で同調圧力に変質してしまいます。こうしたことが、地域社会に蔓延して、「個人情報保護」や「自律を尊重して必要以上に関わらない」等耳障りの良い言葉で他者との関わりを閉じてしまっているのが、地域社会の疎遠とう形になっているのではないかと考えるのです。
もう少し、皆さんが本来持っている他者への気づかいを、周りを気にせず出してみては如何でしょうか。きっと、これまで以上に暮らしやすい街を作れるように思います。私たちの社会は『遠くの親戚近くの他人』が一般化しています。だからこそ他者(近隣など)との関わりづくりに踏み出す時なのだと思います。
宮城県富谷市成田地区を中心に活動している「OOC」(おせっかい・おばちゃん・倶楽部)は、そんな閉塞感のある社会に一石を投じるべく活動を展開しています。今では死語に近い「おせっかい」を復活させよう、もっと言えば東北地方の文化として定着させようと取り組んでいます。この方々が作った憲章を紹介します。
OOC健笑(憲章)
「おせっかい」は、日本が世界に誇る素晴らしい文化です。
見て見ぬふりできず、思わず手をさしのべてしまう「おせっかい」。
その先にあるのは、誰もが安心して暮らせる社会です。
ささやかな一歩から生まれる笑顔を思い浮かべ堂々と「おせっかい」に精を出しましょう。
ちょっと「おせっかいが過ぎる」と感じさせてしまった時は、素直に「ごめんなさい」をいいましょう。
塩梅(あんばい)は少しずつを覚えていけばいいのです。
自分一人で始めたとしても、あなたは決して一人ではありません。
多くの仲間が、あなたのその一歩を励まし支えてくれます。
「同じ想いの仲間がいる」という心強さこそこの活動の大きな目的のひとつです。
思い立ったが吉日。「いいね」と思ったその日があなたの『OOC活動記念日』です。
(註)「おばちゃん」には「おじちゃん、おばあちゃん、おじいちゃん、おねえちゃん、おにいちゃん」を含みます。
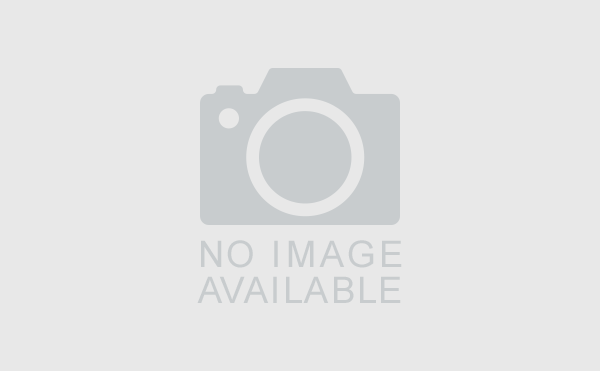
夏休み、公園での出来事にとてもガッカリました。いや「ガッカリ」どころではない、もっと重い衝撃です。そんな経験をさせてしまってごめんなさいという気持ちです。
地域の誰もがリラックス出来、心が穏やかになるはずの公園で無償で振る舞われるコーヒーと手作りクッキー。思い描いただけで私まで癒される場面です。
夏休みにそこに参加した小学生は、大人にまじって、さぞかしドキドキワクワクしていたことでしょう。知らない人には関わらないようにと教えられている現代の子供達が、地域の大人と関わる機会はどんどん少なくなっています。でも、この地域の人達が和気あいあいと談笑する公園なら安心して子供達の地域デビューを見守ってあげられるはず、と。私を始め多くの人が信じていましたよね。
あぁ、それなのに、、、
子供が勇気を振り絞って差し伸べた優しさを、それぞれ理由があるにせよピシャリと拒絶するとはあんまりです。受け取られない何らかの事情や理由は大人としては理解できなくもありませんが、それにしてもです。
この子はどれほど悲しかったか。コーヒーを差し出したその手をどんな気持ちで戻したのか、大人の理由をどのように受け止めたのか、孫の泣きべそ顔と重なって私まで泣きそうです。何と言ったら慰められるでのしょう。
子供にとっては大人が思う以上の心の傷になってしまうのではないか、このままでは大人への信頼は育まれないのではないか。いっときでも早くこの時の気持ちを優しさいっぱいの経験で上書きしてあげたいです。出来るなら縁側日和にお招きして、ばあちゃん達と「たらし餅」を一緒に作り、ばあちゃん達の「もっとくえ、もっとくえ」との優しいまなざしの中、お腹いっぱい食べさせてあげたい。そこでもう一度、みんな優しいな、大人と一緒も面白いなという、経験をさせてあげたいです。
相手の気持ちを推しはかる(忖度)のは大人が先!子供がそれを覚えるのは、まだまだ先で良いのではないかと私は思います。
昨日、OOCの世界大会に参加したにゃんこさん、そのお友だちと四人で夕食を食べに行きました。
その中のお一人(ここではMさんと呼びます)は、昨年10月に移住なさってきた方で、以前、関東の方で小児がんになったお子さんや親御さんのおしゃべりの場を開催していたそうです。以下、Mさんから聞いたお話です。
*******************
がんと共に生きる患者さんやご家族の思いや悩みをともに考える『がん哲学外来』というのが病院で行われています。「がんという病気があっても病人ではない」と語る順天堂大学 樋野興夫医師と1対1でお話をする外来で、お金はかかりません。
私は小児がんのお子さんのメディカルカフェをやっていました。
小児がんになったお子さんの中には、退院していざ学校に戻ると、これまで親友と思っていた友だちがほかのグループになっていたり、体育の授業について行けなかったり、薬の副作用で髪の毛が抜けたり太ったりして、当事者にしか分からない悩みがでてきます。
6割のお子さんが自殺を考えたことがあるという統計もあるんです。
その親御さんにも悩みがたくさんあって、お子さんと親御さんと部屋を分けるなどして、いろいろ感じていることや不安、悩みなどを話してもらっていました。みなさん、たくさん話してくださいました。
ある日、散歩をしていた時に、近所のお寺、金剛院でお掃除をしていた住職さんに出会い、その「おしゃべりの場」の話をしてみました。
すると、「私も子どものために何かをしたいと思っていた。たくさん部屋があるから、ぜひ使ってほしい。ここはいろんな人が集まる場所にしたい」と言ってくださいました。
そのお寺には、「赤門テラスなゆた(なゆたは私たちの身の回りにある「ありがとう」「おかげさま」に気づき、人として限りなく大きな存在であることを感じてほしいと言う願いがこめられている)」もあり、「お寺ごはん」というヘルシーメニューがあります。
住職さんのお返事は、とても嬉しかったです。
その後、近隣の小児科をまわり、「こんなことを始めたい。参加しても良さそうな人がいたら紹介してほしい」と説明とお願いをして回りました。「それはいいね~」と言ってくれる先生もいて、さあやるぞ!というときにやってきたのがコロナ禍!
計画は実現しないまま時間が経ち、他県の土地に移住して11か月が経ちました。
*******************
このような内容を話してくださいました。
そして、話の中で出てきたのが、【これまでしてきて思うことは、自分ではいいと思って声をかけるけど、これって迷惑なのではないだろうか。おせっかいなのではないだろうか。実際、医師から「おせっかい症候群と」言われたことがあるんです・・】と。そして、【他でサロンをやってるところはどんなことをやっているのか知りたい】とのことでした。
【】内の最初のキーワード、今回のホームページの『席を譲るあれこれ』と『OOC』にものすごく被ってくると思い、「読んでほしいものがあります!」とテーブルをドンと叩き(笑)、地域福祉研究所のホームページを紹介したら、まだ海鮮おこげが残っていたのに、さっそくそれぞれのスマホで開いて見てくれていました。『OOC健笑』は、いたく気に入っていただけたようです。
会ってほしい人がいる。行ってみてほしい場所がある。
いつか時間を見つけて、一緒に宮城の方にドライブしましょう、Mさん!!
ハチドリさん、こんばんは
Mさんのお話、とても興味深く読ませていただきました。
小児がんのお子さんやご家族を支える「メディカルカフェ」のような活動は、とても繊細で、なおかつ大きな意義のあるものですよね。そして、その活動に関わっていたMさんが「おせっかいになっているのでは」「本当に役に立っているのか」と不安に思うのは、むしろ真摯に向き合っていたからこその自然な感情だと思います。
わたしも仕事上、ガン患者さんがやご家族が相談に来られることがあり、さりげなくサロンのことを伝えたりしますが、相手の方がどこか困ったような表情をされる場面が少なからずあり、余計なことを言ってしまったか…と、不安になったりどんな風に伝えれば良かったのかと反省したりの繰り返しをしています。
でも、Mさんが“おせっかいかもしれない”と思いながらも行っていたその優しさが、誰かにとって“ほっとできる時間”になっていたんじゃないかなって、わたしは思います。
コロナの影響でその先の活動が計画のままになってしまったことはとても残念なことですが、ぜひ新たな地で活動されることを応援したいと思っています。
支援者が疲れたり、自信をなくしたりするのは自然なことだと、この頃思います。支援者にこそ支えになってくれる人が必要だとも思います。
わたしが開いているサロンは極々小さな集まりで、特別なことはしていません😅おしゃべりの場をセッティングしているだけで、その先は参加される皆さんが作っているのです。
それでもというか、だからこそ楽しみに参加してくださっているのかな?😅
ぜひ、宮城へおいでくださいませ。
それとも福島にお邪魔しましょうか🤗
お目にかかりたくさんお話ししたいですね。
ふらっとさん、ありがとうございます!!
ふらっとさんのコメントを読んだだけでとても温かい気持ちになり、涙が出そうになりました。
本当に想いを持って相談に乗ってくれたり、サロンを開催してらっしゃるんだなと思いました。
実はMさんも「私は何もしてないの」と何度か仰って、そして「集まった皆さんがその場を作っているんです」と話していました。
ふらっとさんもMさんも謙虚な気持ちでやってらっしゃるんですね。そういう雰囲気、振る舞いってとても大切なんじゃないかなって感じています。
宮城になるか、福島になるかはわかりませんが、ぜひいつかお二人がお会いすることができ、想いを語り合ってもらえたらなぁと願っています💕
ふらっとさん、その時はどうぞよろしくお願いいたします。
ハチドリさん、ありがとうございます。
想いを語り合える人がいるって、すごく力になります。
いつの日かお目にかかれることを楽しみに、小さな活動をコツコツと重ねていきます。
いろんなお話ができたらいいなぁ😊
こちらこそよろしくお願いいたします。
ふらっとさん、ありがとうございます。
Mさんからも、「ぜひお会いしたいです」とお返事が来ました。
その時はどうぞよろしくお願いいたしますね。
Mさん、今月末の土日に仙台で行われるイベントに参加するそうです🚶♀️
whats-rfl | リレー・フォー・ライフ・ジャパン https://relayforlife.jp/whats-rfl
このようなものがあるなんて私は知りませんでした。
ラジオ体操の時に、夏休み中の小学生も「珈琲のおふるまい」に参加、素敵な光景ですね。
そんな中で、犬の散歩中の方にお断りされた、とのこと。しょんぼりした姿が目に浮かびます。
私も以前犬の散歩をしていました。正直言えば、その途中で飲み物や食べ物をいただいてもお断りするしかない場合があるようにも思います。いくつか理由があります。「犬は動くので飲み物を手にするのは危ない」「犬が用を足せば、それを飼い主は持ち帰る」などの理由があって(すでにそれは手持ちのバッグの中に入っている、ということもあったりして)、食べ物を受け取るのは躊躇してしまいます。
ここで大切なのは「断り方」なのではないか、と思うのです。「あら、ありがとう!いただきたいけれど、犬の散歩中は難しいの」とその理由を伝えたら、子どもたちは「なるほど!」と新たな視点を得ることができたのではないかしら。「食べてきたからいらなかった」にしても、そのような思いやりやユーモアをもった返答をしていただけたら良かったな、と思います。
自分の理由があるにせよ、まずは相手を受け止める。これは人と対する時にも、また子育てする時にも、とっても大事なことだと思います。受け止めてもらった上で相手の事情を伝えられれば人は素直に受け止めることができたり、傷つくことも少なかったりするのではないかしら。
私も「まずは受け止める」「思いやりとユーモアを忘れない」ということを心掛けたいと思います。
『ここで大切なのは「断り方」なのではないか、と思うのです。「あら、ありがとう!いただきたいけれど、犬の散歩中は難しいの」とその理由を伝えたら、子どもたちは「なるほど!」と新たな視点を得ることができたのではないかしら。』
スマイルさん、まったくもってそう思います。
いろいろなことを体験・学べる『珈琲のおふるまい」ですよね。
そして、『自分の理由があるにせよ、まずは相手を受け止める。』という言葉もとても響きました。そうですね。私もこころがけたいと思います!
ありがとうござました!
この前のスマイルさんに書いた私のコメントが言葉足らずだったと思うので追加で書きます。
今回の内容を読んでいて、朝ごはんを食べて来たからと珈琲と手づくりクッキーを受け取ってもらえなかったと言う、小学生のお子さんのことが実は気になっていました。
きっと初めてのお使い状態で、緊張でいっぱいの全身全霊で、知らない人に声をかけたかと。
確かに犬と散歩中の人はお腹いっぱいだったかもしれないし、手が汚れていたり、ふさがっていたかもしれない。そのことをやさしく丁寧に伝えることはもちろん大切なことです。
でもその前に「わぁ、おいしそうだね。どうしたの?ありがとう!」と、まずは持って来てくれたクッキーだけでも受け取り、そのお子さんに感謝の気持ちを伝えることが一番大切だと思いました。それから「でも、さっき朝ごはん食べてきたばかりで今はお腹いっぱいだからお家にもらって行ってもいいかな?おいしそうなクッキー、おやつに食べたい!」とここで食べれないことやあとから食べることを伝えることができたら、そのお子さんの満足感や自己肯定感がとても高くなるのではと思うのです。
『まずは相手を受け止める』ってすごく大切なことですよね。
こんな場合の忖度は大いにあっていいと思うし、大人としての大切な振る舞いのようにも思います。
電車やバスで席を譲ると言う行為でも、いろんな考え方があるようですが、「譲りたい」と思ってくれた人には、まずは「ありがとうございます!」の気持ちをしっかり伝えることが大切なのではないかと思いました。
この講義で先生が述べてくださったすれ違う心や微妙な気持ちは、誰しも経験がおありなのではないでしょうか。
人はそれぞれに違います、差し出された想いに必ずしも答えることができない事情も抱えていたりする、おせっかいするのも自由なら、どんなに心をつくされたことでもお断りする自由はあると、そう思えたら良いのではないでしょうか。
誰かの在りようから自分が傷つくことはないのだと、出来事にに対するこだわりを手放し、自分の勇気や想いが空回りしたことや哀しさも手放し、それでも人を想うことをやめない、そのためにOOCがあります。
OOCオリジナルのバッチを作りたいと、みなさんにデザインの投票をお願いしたときに、ダントツの一位で「ともし火」に決まったのは、人を想う気持ちは孤独と隣り合わせで、哀しさを感じたとき心に灯すともし火があったらと、みなさん同じ思いがあったのではないでしょうか。
人を想う気持ちを大切にしていくためのセルフ応援団として、ともし火バッチがあります。
OOCを名乗っての活動はありませんが、ふと差し出す手をやめないために、心に灯すものであって欲しいと願っています。
冒頭の小学生がしょんぼり戻ってきたら、OOC魂にともし火を着火!「あらぁせっかく声をかけてくれたのに残念ね、お腹がいっぱいだったのかな、言い方が優しくなかったって?お話しするのが恥ずかしい方なのかもね、声をかけた君は偉かった、お年寄りに優しくしてくれてありがとう」と、こんなおせっかいおばちゃんでありたいです。
人はわかりあえないのだと納得できれば、稀に心から通じ合えた時の喜びは倍増するのだと思いました。ご参考まで、近ごろ読み返していた本をご紹介します。
講談社現代新書 平田オリザ著「わかりあえないことから」
先生、喜びが倍増する場をありがとうございます。
いくこさん、OOCについてあらためて想いを伝えてくださってありがとうございます。
いくこさんがずっと言っていたのが「バッジがあれば」ということでした。投票の結果、だんとつで「ともし火」に決まった時、とても感慨深いものがありましたね。
コメントの中の『人を想う気持ちは孤独と隣り合わせで、哀しさを感じたとき心に灯すともし火があったらと、みなさん同じ思いがあったのではないでしょうか。人を想う気持ちを大切にしていくためのセルフ応援団として、ともし火バッチがあります。』という文章に、胸にこみあげるものがありました。
少しでも地域を良いものにしたい、子どもたちにとって安心できる社会にしたい、そう願って「せずにはいられない」想いを持つ人は、時に孤独を感じることがある。それは「試し」のようなもので「それでもあなたはやりますか?続けますか?」と問いかけられているのだと思うのです。そんな時、遠いあの地でもこの「ともし火」を胸に今日もできることをやっている人がいる、と思えることほど支えになることはありません。私もOOCとはそういうものだと理解していますし、そこに心から共感、賛同しています。
『OOCを名乗っての活動はありません』ともありますが、そうですよね。誰かがどこかが中心となって活動している実態があるものではない、そこがOOCのオリジナルなところ。「一人で始めたとしても、あなたは決して一人ではない」「同じ想いの仲間がいるという心強さこそこの活動の大きな目的のひとつ」という健笑(憲章)が物語ってくれています。富谷市成田中心で活動しているものではなく、世界中どこでも「誰かを想ってささやかな行動を起こした人」こそが活動の中心です。
それぞれの地域に課題があり、それはその地で力を合わせて少しでも良いものにしていくしかない。バッジそのものを持っていなくても、「ともし火」を胸に灯すことはできます。その胸の「ともし火」は同じ想いの人と共鳴し、駆けつけることはできなくても互いを支え合い励まし合って、それぞれの地域を灯す力になると信じます。
スマイルさん
「バッチがあれば」そうなんです、よく覚えていてくださいました。
どこかで誰かが人を想っていると、自分を励ます小さなお守りのようなものがあったらと考えていました。
その気持ちをこの場に書きこみましたら、みなさんからたくさんの共感の言葉を寄せていただいたのでした。
それは本当に思いがけないことでした、そしてOOC世界大会と名付けたオフ会の開催へと繋がったのでした。
会場が町内会館とはいえなにしろ世界大会ですから真剣でした。健笑(憲章)、わたしたちの約束(会則)を作るための言葉を選ぶやりとりするうちに、この場に集うみなさんの想いと姿、頑張りにふれて、「私にもうバッチはいらないかも」とも思ったのでした。
スマイルさんの言葉のとおり、『それぞれの地域に課題があり、それはその地で力を合わせて少しでも良いものにしていくしかない』遠くで頑張っている人のところへ馳せ参じることはできない、でも共感という応援をすることはできると確信しています。
心がすれ違うとき「おせっかいだから」と笑ってすごし、次のおせっかいに精をだしましょう。
みんなが人を想い行動する時世の中は変わっていくのではないでしょうか、おせっかいしましょう。