民生委員児童委員試論』第3講『私が行っている民生委員児童委員とての活動』
民生委員児童委員の主な活動(制度で規定している内容)は、民生委員法第14条では次のように規定されています(児童委員としての活動も対象舎が違うだけでほぼ同じなので割愛)。
1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
今月から、民生委員法で定める活動内容について、一項目ずつ私自身の解釈で行っている具体的な内容を書いていきます。
『民生委員児童委員試論』第3講では、「1住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと」について書きます。
この項目において、全ての民生委員児童委員が行っている最も基本的な活動内容は、高齢者独居世帯や老老二人世帯及びその他何らかの課題を有する方々を対象に、1ヶ月に1回定期的に居宅を訪問し、お話しを聴いたり生活の様子を観察することです。
健康上の悩みや介護・生活課題等多岐多岐に渡ります。民生委員児童委員はこうしたお話しに耳を傾けつつ、合わせて生活の様子を観察して、課題が潜んでいないかなどにも配慮しながらお話しに耳を傾けます。
民生委員児童委員によっては、訪問した際に留守でお目にかかれない場合、再度の訪問をして出来るだけ直接お目にかかり様子を聴くようにしている方も多いようです。民生委員児童委員にそうさせるのは、「孤独死」の心配からです。マスコミ等々で孤独死が社会問題として報道されます。家族構成が老老二人世帯や高齢者単身世帯が多くなり、孤独死のリスクが決して他人事や遠くの出来事ではなく、身近にもあり得る状況があるからです。
お話しを聴き、必要に応じて公的機関(多くは、高齢者が多いので地域包括支援センター)へ相談内容を伝え必要な対応を促します。民生委員児童委員の役割は、自らが解決に奔走するのではなく、必要な社会資源に「つなぐ」ことです。こうしたことから、対象者のお話をしっかり聴き、課題を整理して必要な社会資源(関係機関)につなぐまでが役割です。それ以降は、関係機関の役割になります。
民生委員児童委員活動の「入り口」は、この「住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと」です。全ての活動はここから始まります。この為、最も大切な活動と言えます。

さて、この最も大切な活動「住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと」に対して、私はどのように対応しているかを以下に書きます。
①月に一回程度、定期的に居宅を訪問し、日々の暮らしの様子や「気がかり」なこと等を伺います。
・その際、気を付けている問いかけの言葉があります。「何か困っていることはありませんか」「何か問題はありませんか」と、いう問いかけはしません。理由は、困っていることや問題には、個人差が大きく、「こんなことで困っていると言って良いのだろうか」等々と考えてしまい、「困っている・問題」という問いに、口を開くことを躊躇う傾向があるからです。
・この為、私は「気がかりなことはありませんか」と、聴きます。こうした聴き方によって、間口を広げ気になっていることのレベルを下げて口に出しやすいようにしています。
②訪問して不在の場合は、改めて伺うことはしていません。何らかの訪問した足跡を置いてくるだけにしています。足跡は、「民生委員児童委員新聞」です。郵便受けに入れてくるので、民生委員児童委員が訪問したことは、これで分かります。
③民生委員児童委員が訪問したことを知って、折り返し電話等で連絡を下さる方は、ほぼ皆無です。それでも良いのです。訪問して来たこと(繋がっていること)を自覚してもらえれば、それで十分だからです。
④定期の居宅訪問は、お話しを聴くだけではなく日々の生活の様子を観察できる機会でもあります。玄関周りや庭の様子、立ち振る舞い、身なりや整容、表情や顔色、ろれつ等々で身体的健康状態。加えて、話題の内容がポジティブかネガティブな等によって精神的健康度もある程度想像出来ます。お話しする内容の繰り返しや季節感のズレ等々によっては、MCI(軽度認知障害)を疑ってみることも有りかも知れません。
まとめ 『1住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと』の目的
・月に一回程度、定期的に居宅を訪問する目的は、対象者の生活の様子を把握することではありません。居宅訪問による生活の様子の把握は『手段』に過ぎません。大切なことは、『予見すること』です。課題が生ずる前に対象者の様子や振る舞いから課題を予見し、必要な社会資源に情報を提供し、専門的対応と繋がることです(予防福祉)。
・同時に、地域生活をつつがなく営んで行くに際して、民生委員児童委員と繋がっていることは大切なことだと思ってもらえることです。頭の片隅に『民生委員児童委員』が置いてあることです。
・民生委員児童委員は、対象者全員を把握し日常的に支えることは不可能です。また、行政からそれを期待されているとは思っていません。大切なことは、高齢者自身に生活上の課題が生じたときあるいは何らかの課題が起きそうと感じたときに、「民生委員児童委員」の存在を思い出し何らかの行動を起こしてもらうことです。例えば、民生委員児童委員に相談する、地域包括に相談をする等々です。
・この為、最も大切なことは民生委員児童委員と繋がっていること『掛かりつけ民生委員児童委員』を持っていることです。
この様に、私は、出来るだけ民生委員児童委員からの一方的なアプローチだけではなく、当時者本人またはご家族から民生委員児童委員に連絡が来るようになることを願って、上記の様な対応をしているのです。
これから民生委員児童委員になってもイイかなって思って下さる方に申し上げます。民生委員児童委員自身が対象者の全てを把握しようと思わなくてイイです。現実的にも難しいです。それよりも大切なことは、何か起きそうなときに、民生委員児童委員の門を叩いてもらえるように敷居を低くし、いつも門を開いておくことです。それだけで地域住民の『掛かりつけ民生委員児童委員』として十分に役割を果たせます。
それだけで良いのです。是非、地域住民の役に立ちたいと思っている方は、民生委員児童委員になることも選択とてして持って下さい。きっと『情けは人のためならず』となり自己実現の機会になるものとお勧め致します。
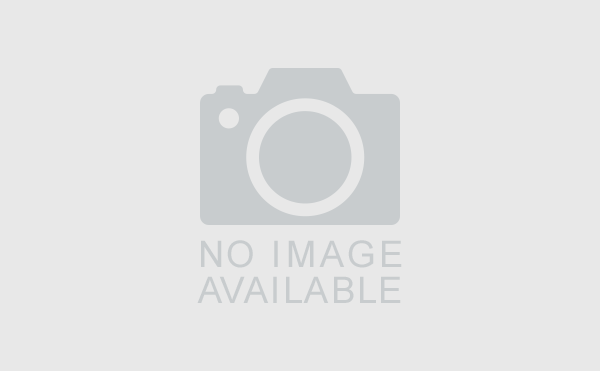
ホームページが更新されていたということは、アドレナリンが少しづつでも湧き上がってきているということでしょうか?
永平寺への道のりをひたすら進まれたように、気力、体力が確実に回復されているのですね。
良かったです。
さて、今回の記事を拝見し、「気がかりなことはありませんか」というお声掛けに心が温かくなりました。
相手の方が安心して気持ちを話せるように寄り添う姿勢は、わたし自身も日々の訪問の中で大切にしていきたいと感じました。
「民生委員児童委員新聞」の取り組みも誰しもができることではなく、毎月の発行を継続されていることに感銘を受けております。
民生委員活動の中で、声のかけ方や関わり方に悩むことがありますが、今回の記事を励みに自分なりに工夫を重ねていきたいと思います。
・・・そういえば、訪問していると訪問先の方から必ずと言っていいほどわたしのことも気にかけていただいています。「暑い中回ってて、あんだごそ大丈夫すか?」「休んでいがい」なんて(笑)一方通行ではなく双方向の関りがあるなぁって、ほっこりしながら活動しております。
「情けはひとのためならず」という言葉の意味を改めて実感させていただきました。
ありがとうございました。
ふらっとさん、こんばんは!
『一方通行ではなく双方向の関りがあるなぁって、ほっこりしながら活動しております』っていいですね😉!
双方向、大切ですよね!!
ハチドリさんこんばんは
双方向の関わりができているのは地域性もあるし、前任者が引き継ぎを丁寧にしてくださったおかげと思っています。
いろんなことに感謝しながら活動しております😊
ふらっとさん、こんにちは!
このホームページに新着記事のコーナーを作ってもらい、見ていたらふらっとさんとのやりとりにすぐに辿り着けました。
実は、OOC世界大会のときにふらっとさんと同じグループだったと思うのですが、にゃんこさんと言う人、ふらっとさんとお会いしてサロンのことなどをお聞きしたいのだそうです。
今日は職員健診だったのですが、そこで話しかけられました。
詳しくは後ほど、先生か鈴虫さんかを通して連絡をさせて欲しいのですがよろしいですか?
ハチドリさん、こんばんは
本当ですね😊
コメントにもすぐに気づけて、ありがたいですね。
わたしでお役に立てるのでしたらぜひ、お目にかかりお話しできたら嬉しいです。
ご連絡お待ちしております。
先生、鈴虫さん、よろしくお願いいたします。
いつのまにか記事が更新されていました。
先生、お疲れのところ、ありがとうございました。
身近なところにかかりつけ民生委員がいることで、何かあったときに連絡が取り易く、適切な関係機関につないでいただける、そんなシステムになっていたら地域で安心して暮らせるなと思います。
質問があります。
今回のテーマである、先生もとても大事と言う、民生委員児童委員の活動の1番目に書かれている「住民の生活状況を必要に応じて把握しておくこと」ですが、この訪問対象となる方々を最初にどのように把握するのか、また新たに対象になる人の把握はどのようにしているのか教えていただけますか?
①役所の民生委員を担当する課からの情報提供
②前の民生委員からの引継ぎ
③自分で発見(ご近所や本人からの連絡など含む)
④前回記事にあった悉皆調査の時など
⑤その他
よろしくお願いいたします。
ハチドリ様
コメント有り難うございます。
ご質問へのお答えですが、①行政からの情報提供はなく、②から④迄を組み合わせて対象者の把握を行っています。
対象者で特に意識しているのは、介護保険や障害者自立支援制度等々の何らかの制度の網に入っていない方々を特に意識して把握に努めています。
介護保険制度の中いいる方々は、地域包括やケアマネージャ等によって把握されており、更には定期の訪問も義務づけられています。
この為、そこから漏れる方々こそ、私たち民生委員児童委員の役割だと考えています。