地域づくりに関わる社会学
『かじってみよう社会学Ⅱ』第3講目の今回は、地域づくりを進めるに際しての視点を取り上げます。
地域活動で良く聴くお話しに、「女性は様々な機会に外に出てくるけど、男性はなかなか出てこない」「地域の方交流を図るためにお茶会を企画しても男性はほとんど参加しない、いつも女性ばかりしか集まらない」があります。
町内会活動を進める役員さん達や地域包括ケア推進を担う方々に共通してあるのは、こうした「男性が地域と関わらない」「自宅に引きこもっている」という悩みです。こういった現状に対して、社会学に何か参考になるヒントは見いだせないか考えてみました。
「お茶会に男性が参加しない」という現象に対して、私は次のようにその理由を説明しています。
男性と女性の会話の構造に根本的な違いがあるのではないか。女性はコップ一杯の珈琲で1時間もおしゃべりできるが、男性は5分も持たない。料理のこと、育児のこと等々、日常生活に関わることが次からつぎに、それも具体的な内容が話題に上がるのです。ある方は、「私たちのお話に無駄な話はない」と豪語します。
一方の男性は、そうした女性の会話について行けません。さっきまで話していたことが、今度は全く違う内容に簡単に移っていきます。女性には「生活上のこと」という共通項があるのかも知れませんが、男性には「さっきまでの話と違う」としか受け止められないのです。加えて、日常生活場面を下にした、具体的で現実的な内容に対して、男性は制度や仕組みといった枠組み的な内容に関心があり、具体性に欠けるところがあります。
男性の場合はお茶のみでは集まらないのでお酒は必要だと言われます。でも、これは少々的外れのように思います。お茶からお酒にすれば良いのかといえば違います。男性の場合は、お酒を頂き、天下国家を延べます。当然、趣味に関する話も出ます。これは女性にもあります。しかし、女性の場合は、やり方や材料などに関心が向きます。それに対して男性は、使っている道具に関心が向けられ、いつしか道具自慢になったりします。同じ趣味にしてもこれだけ違いがあります。
一般論ではありますが、こうしたものの見方や関心の向け方に大きな違いがあり、「お茶のみの場」では交わることは相当難しいのです。
更に決定的なのは、お茶会に対する受け止め方の違いです。多くの場合男性は、前述の女性が豪語した「私たちのお話に無駄な話はない」とは受け止められず、多くはお茶会(お茶のみ)を「ひまだれ」(生産に繋がらない行為は無駄なこと)といい、それに組みすることを避けます。
様々例を引いてお話ししましたが、あくまで一般的傾向であって、男性と女性の行動を決めつけているわけではありません。当然、「私は違う」という声があることは承知していていてのお話しです。
では、男性を巻き込むにはどうするかです。男性には「ひまだれ」ではない大義(役割とも言えます)が必要です。お茶会にしても、「お茶を飲む」という参加の仕方ではなく、「お茶を出す」方に視点を置く必要があります。飲むのが珈琲などの場合は、お茶よりも非日常的感覚も加わり、道具や技術に関心が向くので、男性を巻き込むときに、珈琲はとても有効です。
私が知っている活動では、「Origina lBlend」珈琲を開発し、その珈琲にお気に入りの名前を付けて皆さんに振る舞っています。これなどは、男性に参加して頂く仕掛けとしては極めてすぐれた事例だと思います。女性は飲む人、男性は淹れる人。これが絵になっているのです。
この様なことを意識して地域の居場所づくりや地域活動を考えてみては如何でしょうか。役割は、想像以上に大きな力を発揮ます。だまされたと思って実践してみて下さい。
女性・男性に差はないと思います。でも、ものの考え方や考えを形に移す時のやり方には違いがあるように思います。なので、その「違い」を意識して様々な活動を設計してみては如何でしょうか。
繰り返して言いますが、男性には役割が必要です。そして、何らかの困難さや技術的向上心を刺激する仕掛けが必要です。地域で良く行われる「お茶会」の場でも、こうした視点を意識して設計すると多少は参加者が増えてくるように思います。同時に、人数が問題なのではなく、関わる人達自身が「楽しい」と感じられることが最も大切です。人と人との関わりには、単にその場を共有するということだけは無く、そこに何らかの役割を必要とします。特に、男性にはその傾向が強いです。
「心」とは、何処にあるのか?という問いに、ある方は「心とは人と人との間にある」と答えています。他者との関わりに中に自分の意思や考え方が生じます。そして、同時にその関係性には何らかの役割関係が生じます。ここに、自分らしさや行為の原動力があります。人と人(他者)、人と社会(社会制度)の関わりが様々な行為を引き出すのです。



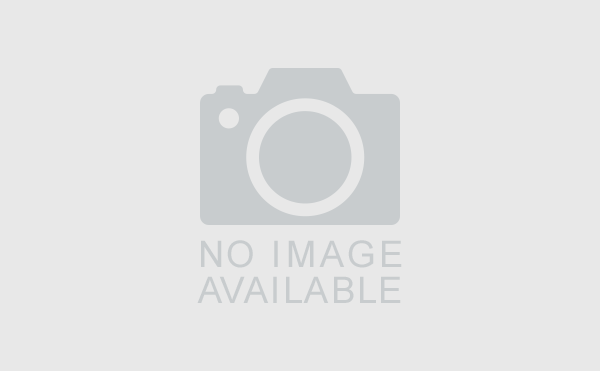
「お茶会に男性が参加しない」事について、女性と男性の違いを並べて説明していただきました。
「女性の会話は内容が次々と変わり、男性はそれについていけない」というのを聞いて、確かにその通りだなぁと私も少々耳が痛いです💦
それで考えてみました。
女性の会話はなぜ次々と違う内容が出てくるのか。
例えば家事をする時、お料理をしながら、じっとひとつの鍋を見つめている人はいません。
使った道具を次々と洗い、2、3品のおかずが一緒に食卓に並べられるように手元も頭もフル稼働です。
途中で洗濯が終わればそれも気にかけ、子供達が帰宅すれば今日の様子を聞きます。
極たまに主人が料理をすると、必ずと言っていいほど数々の調味料や調理道具が流しいっぱいに並びます。
ひとつのことにこだわり、最高に美味しい物を作ることに専念するのです。
その様子に黙って後始末をするのは妻の仕事です。
男女の性差とは、お互いに補い合うためにあるもので、喧嘩のタネにすべきではない。してはいけないんです、暮らしにくいから(笑)
多くのおばちゃん達はそういう日常を送っているから、会話があちらこちらに飛ぶことにも違和感ないのでは無いでしょうか。
待てよ、会話と行動の関係、たまごが先か鶏が先かは定かではないです。
前説が長くなりましたが、そもそも人が家に引きこもらない様にと企画をするのが女性だから男性がそこに参加出来ないのかもしれません。
男性による、男性の為の企画をもっと打ち出してくれたら女性があの手この手と悩むことも減るのではないかなぁ。
男性のみなさん「おせっかいcafe」を見習って、是非何かご自身が楽しめる企画を展開して見せて下さい♫
ご報告を楽しみにしております😊
お久しぶりです。
本間先生、75歳を迎えるのに、福井県の永平寺まで700キロ歩いたとは、驚きと先生の想いに感動しました。ご家族の理解と協力あっての成し遂げられた事だとも思いました。
動画をゆっくり見て、感じた事を書きます。
先生は、いろいろな方々と連携して、いろんな形で人々と交流をして、社会、地域で独りぼっちの人をつくらず、1人1人に楽しい人生を送って欲しいと思い活動をしてるんだなあと思います。
しかし、先生自身は、時々独りぼっちになり、四国お遍路の旅、今回の仙台から福井の永平寺までの旅をして、孤独で厳しい日々を経験してますね。
だからこそ、道中誰かに声をかけられて、1人じゃないんだと嬉しく感じたのではないでしょうか。
それこそ先生が、手を差し伸べてきた人々の気持ちと同じだと思いました。
素敵な動画を見せていただき、ありがとうございました。
メッケ様
いつも気に掛けて頂き有り難うございます。
私の座右の銘は『刻苦勉励』です。これは、自分自身に向けた姿勢なのですが、自分自身の振る舞いを顧みるたびに、人様の支えがあっての自分なのだと思えます。「四国八十八ヶ寺歩きお遍路」や今回の「永平寺への未知・みち」を通して、改めて人様との関わりに中で自分があるのだと強く感じています。「自分を見つめることで他者の存在を知る」他者との関わりの中で自己が存在するという、社会学で学んだことを改めて感じています。コメント有り難うございました。山河自然
先生、コメント書く日を間違えてしまいました。
7月28日の動画についての感想を書いたのに、今回のも続けて読んでいて、間違ってこっちに書いてしまいました。
すみません💦
むかし暮らしていた田舎でも、今もそうですが、地域の中の「これ!」という決めごとをする時や力仕事、環境整備には、男性が活躍しています。実家の方では、『ろくしんこう』と言う葬祭に協力しあう『講」もありました。そんなときも男性の出番だったと思います。
お隣近所とのお茶っこ飲み、昔はよくあって、そのときからそこにいるのはあらかた女性で、男性はお茶は飲んでも仕事があってお茶っこ飲みはしないという感じだったような気がします。子供たちもみんなで遊んでいました。そのような中で、地域のつながりとか、助け合いとか、悩み事・困りごと相談の場とか、仲間づくりとか、そのようなことは自然と当たり前にできていたのかもしれません。
92歳で亡くなった私の母は若いころから外で仕事をしていて、核家族でお茶っこ飲みの習慣はなく(そのためか、私もお茶っこ飲みというのはなんとなく苦手だった)、こんなふうに女性も外に出て仕事をする人が増え、お茶っこ飲みなどは少なくなっていった反面、核家族化、高齢者は増え、地域のつながりとか、助け合いはますます大切になってきたのではないかと思います。最初に書いた実家の方の『ろくしんこう』も維持するのが難しくなってきたようです。
地域の中では、日頃の挨拶をはじめ、立ち話、お福分け、ラジオ体操、圧倒的に少なくなったけどご近所とのお茶っこ飲みなど、いろんなつながりがありますよね。そんな中で、私の記憶だと介護保険が始まる少し前あたりから、地域の中でサロン風のお茶っこ会が開催されるようになったように思います。前の前の職場で、さまざまな協力をいただき、42行政区で『元気ふれあい塾』というのを立ち上げたことがあります。家庭訪問をしていてその必要性を感じたのでした。25年以上経った今でも続いていると聴いてとても嬉しく思っています。
私も、お茶っこ飲みは苦手・・なんて言ってないで、今は地域の中で集まりがあったらなるべく参加するようにしています。私が住んでいるところは、原発事故の影響で一時全員避難し、なかなか元の住民は戻ってなくて人口はまだまだ少ないのですが、移住者の方も多く、集まりに行くと知らない人と知り合ったり、普段聞けないお話が聞けたりするいいチャンスだと思っています。
前置きがだいぶ長くなってしまいましたが、人は誰でも「役割」があると言うことは、それをその人がどんなふうに認識してるかはそれぞれですが、自己実現をしていくうえでも大切なことだと思います。本人も周りも幸せになれる「役割」、そんなことを意識して考えていけたらと、あらためて思いました。
そして、何より『楽しい』と感じられるように!
『女性はコップ一杯の珈琲で1時間話も話ができる』と書かれていましたが、本日の朝一番から夕方までの私の職場での会話です。
昨日、知り合いから、とてもかわいいハートの形をした『カットバン』をもらいました。
それを同僚に見せながら「こんなかわいいカットバン、どこに貼ろうかしらね」と言ったら、「カットバンって何ですか?」と言う人がいて、「ええ~(*_*;」となってしまいました。
「キズに貼るやつのこと、みんなは何て言うの?」と聞いたら、50代の3人は『絆創膏』と答え、60代の3人は『カットバンと言う』とのことでした。私もその一人、なんなら「キズバン」とも言い、絆創膏はぐるぐるになったやつを言います。
昨日は家に帰ってからもずっと気になり、宮城のお友達にもメールで聞いてみたら、60代の3人は『カットバン』、50代の1人はやはり『絆創膏』だったのです。
で、本日、朝一番の職場での話題はこの宮城の友だちの『カットバンと絆創膏』の報告から始まりました!!(笑)
すると、ネットで調べてくれた同僚がいて、下記のような面白いことがわかりました。
【キズバン方言】
絆創膏は、地域によって様々な呼び方があり、その背景には商品名が由来になっていることが多く、これらの呼び名は、各地域で最も普及した絆創膏の商標名がそのまま一般名称として使われるようになったと考えられています。
1.キズバン:富山県
2.バンドエイド:関東、東海、近畿地方
3.カットバン:東北、中国、九州・沖縄地方
4.サビオ:北海道
5.リバテープ:九州地方
夕方、外から帰ってきた20代の職員2人に同様の質問をしたら、『カットバン」と答えたので、なぜか「ワ~!!」と歓声が巻き起こり、大笑いしました。
そして横浜から来てる60代の人は『バンドエイド』とのことで、「やっぱりね〜」と、またまた大笑い!
年齢は関係ありませんでした。
確かにこれだけの話題なのに、女性の特権?一日中、ずっと楽しむことができました。
ありがとうございました。
実に面白く、興味深い内容です。
何度も反芻し、考えてみたいと思います。