雲水(修行僧)をまねてみよう
市井の人となって2週間余り、休日は良いのだが平日は罪悪感がある。ただ何もせずに家にいるのがしっくりしない。時間に追われる生活ばかりして来たので、いざ自由な時間が手に入ると、どの様に使ったら良いのか皆目見当が付かない。何とも贅沢な悩みなのだが、私にとっては未知の世界で心細い。
そんな中で、毎日やることを決めれば良いのではないかと思いつき、参考に永平寺の雲水(修行僧)の日課をのぞいてみた。
永平寺(福井県にある曹洞宗の大本山)では、多くの雲水(修行僧)が厳しい修行に励んでいます。200人から300人の雲水は、1年から2年の間、厳しい修行の日々に明け暮れます。雲水(修行僧)は、朝の起床から夜の開枕(就寝)まで、厳しい規律と作法に則った修行に努めています。
朝4時頃から夜9時まで、朝昼晩3回の勤行(読経)や延べ5時間近くの座禅、主に掃除を行う作務などの修行が続きます。休みは、4と9のつく日だけで、参禅などが放免されるが外出などはいっさい出来ないという厳しいものです。
雲水の一日はは以下のように定められています。
・03時30分(夏期)4時30分(冬期) 起床・洗面、暁天(きょうてん)座禅 線香一本が燃え尽きる時間とされる一炷(いっちゅう)の間でおおよそ40分。この時間、境内には大梵鐘が1分50秒間隔で18回鳴り響く。
・05時 朝課(朝の勤行)
・07時 小食(朝の食事)
・08時30分から10時 作務(堂内や境内の掃除)禅門では、古来から「一に掃除二に看経」といわれ、掃除は心身内外の塵を払い清める修行とされてきました。
・10時 座禅
・11時 日中諷経(にっちゅうふぎん)昼の勤行
・12時 中食(ちゅうじき)昼食 中食には、生飯(さば)という作法がある。食べる前に麦飯を七粒取り、外に設置されている生飯台に置き、鳥獣や無縁仏に供養する。
・13時から14時 作務
・16時 晩課諷経(ばんかふぎん)夕方の勤行
・17時 薬石(夕食)
・19時 夜座 一炷の時間(約40分)を2回2時間弱の長い座禅の時間
・21時 開枕(消灯・就寝)
ルーティン(routine)とは、決まった手順、おきまりの作法、日課などと訳されている。毎朝決まった時間に起きて決まったルーティンをこなし余裕のある時間を過ごす。その結果、生産的な時間の使い方や日々との向き合い方に自信が持て、丸一日ゆとりある時間を過ごせるという。自己肯定感の低い私には、使えるかも知れない。
これは試してみるしかない。ルーティンを決めるときは、雲水に日課を参考にし、これまでやったこともない家事や掃除も修行と思えばやれるかも知れない。今朝、毎朝行っていた読経に加え庭の草取りをしてみた。息が切れた。これはやはり修行だ!
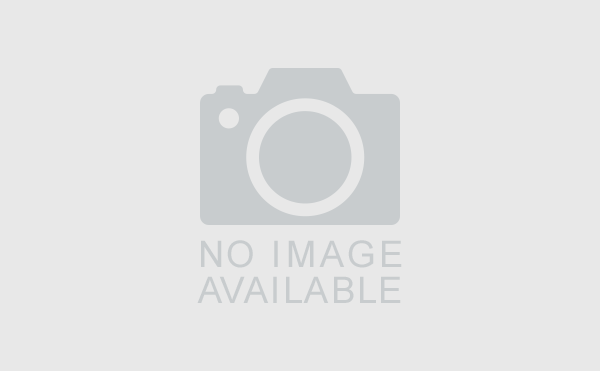
長い間社会不在をしたために都会ででの生業や人間関係を失くし北陸に移住して来ました。
しかし、僕は運の良い方で、市町村に行ってこれまでの経緯これからの復帰に向けての計画をお話させて頂いたところ、受け入れ可能で、しかも「どうか
やり直して下さい」とまで言って下さり、今支援に向けて準備調整を行って下さっています。
これも単に身仏様のご慈悲と思し召しと心得、懸命に取り組んで行く所存でございます。
本当に有り難うございました。
「雲水(修行僧)をまねてみよう」を読んでいただき有り難うございました。
加えて、貴重な体験を投稿いただき重ねてお礼申し上げます。
人との関わりに疲れた自分を、地域社会が暖かく向かい入れてくれたとのこと。
このことは、おっしゃるように、何かの御縁(神仏の慈悲)なのかも知れません。
私は、同時に前田様の真摯な生き方や自分との向き合い方に、北陸の方々が共感してくれたのではないかと思います。
どうか、その様な自分を信じ、他者の優しさを信じ、新たな進むべき道を歩んで下さい。
このhp地域福祉研究所は、こうした振る舞いに大いに勇気づけられ、参考にする方もいらっしゃるかも知れません。
気が向いたら、その後の様子などを書き込んでみて下さい。私自身も読んでみたいと思います。
今回の投稿、有り難うございます。