倶楽部活動『チョイ足しボランティア』
第4月曜日は、倶楽部活動(課外活動)。個々人の「観たり、読んだり、聴いたり、つくったり」等々の活動を共有し「まねっこ」しあう場です。今回は、僭越ながら、私が関わっている活動をご紹介します。
私が住んでいる泉区長命ヶ丘四丁目の近隣住民を構成員とする「晩酌の会」です。晩酌の会は75歳以上男性6人で構成されています。2年前の2023(令和5)年10月7日に第1回晩酌の会(飲み会)が開催され、丸2年になります。
民生委員児童委員として地域を廻っている中で、一人の方から「晩酌を一緒にしませんか」とのお誘いが事の発端です。多くの男性が日常的にやっているだろう「晩酌」、これは使えると咄嗟(とっさ)に思いました。そこで、同じ班に方々に声を掛け、月一回近隣にある中華料理のお店を開場に、近隣の男性が集まって晩酌をすることにしたのです。
私のもくろみは、孤立防止を兼ねた高齢男性の社会貢献です。でも、一気に「社会貢献」というと腰が引けてしまいます。そこで、「晩酌」という日常的な行為を外に出る第一歩にして、顔なじみの関係を築いて行く。その先に少しずつ外に目を向ける機会を設け「社会貢献」という目的につないで行こうと考えたのです。こうしたことは、高齢男性の社会的孤立を防止し、地域と関わるという成功体験をとおして「健康寿命」の延伸そして「貢献寿命」という新たな概念を糧に自己実現の機会になるのではないかと考えたのです。
私自身には、晩酌の会の「場所」にもこだわりがあります。それは近隣にあるお店(この場合は中華料理屋さん)は、「社会資源」だということです。近隣に歩いて食事をしたり、チョットお酒を飲んだりするお店があるというのはとても貴重で、住み慣れた地域で暮らし続けるという視点に立ったとき、これも日常生活の余暇、憩いの場に於ける社会資源だと思っているのです。そうしたお店が成り立っていくためにも、上手く使うと言うことも、私たち地域に暮らす者として必要な配慮ではないかと。
この様なことを考えながら、毎月定例の重ねながら、社会貢献の機会を提案し、成功体験を積み重ね2年になりました。以前、たまに参加させて頂いていた富谷市成田地区の活動は、既に10年という歳月を重ね、その間コロナ禍を乗り越え多彩な活動を展開しています。その様な活動を見ていると、まだまだひよっこです。「続ける」というのは「始める」ということより遙かに難しいです。これまでは、物珍しさで続けられましたが、これからはキットそうはいかない。これからこそが、本番と考えています。
現在、やっていることは、定期の「晩酌」、たまには、対象範囲を広げて、ゲストスピーカーをお呼びして話題提供をしてもらい、それをお酒のつまみにして語り合う「拡大晩酌の会」。良く聞かれる男性版の地域の集まりは、だいたいここで終わりです。でも、「晩酌」は手段であって始めの一歩に過ぎません。そこを下にして何らかの社会的役割を担うことが目的です。
こうしたもくろみ下に、手段としても「晩酌」を定期的に行い、その先に地域内の様々な活動に着目して、それら既存の活動のチョコッと付け足しをする「おせっかいCafe」を行っています。75歳以上高齢男性に本格的な珈琲の淹れ方を喫茶店のVaristorに教えて頂き、そのスキルを使って、様々な場で珈琲を淹れています。
現在、おせっかいCaféは様々な場で行っています。健康づくりとして行われている公園でのNHKラジオ体操の場。町内会主催で行われている、ほほ女性のみの「ふれあいサロン」(私は「女子会」と呼んでいます)の場。児童センターで行われている親子を対象にした「遊びのおもちゃ箱」の場。等々です。おせっかいCaféは、次第に地域から声がかかるようになってきました。最近では、ことも会とのコラボや泉区社協で行われる地域活動事例報告会で活動報告をすると共に「おせっかいCafe」を開店します。
おせっかいCafé以外では、地元の小学校を開場に「剪定教室」を行っています。私の計画は、自宅の庭の剪定技術を習得してもらい、その次には小学校の庭木を剪定するボランティアの人財になって頂くことです。ここに行くためには、もう数年回数を重ね、一定の人数が剪定技術を持てるようになってから提案してみようと考えています。
たいした活動ではないのですが、身の丈に合った「近所づきあい」の延長線上にある行為として行われるようになれば良いなと思っています。
今年の課題は、地域の各機関との連携協働です。町内会、地域包括、地区社協、児童センター、子ども会、小学校等々です。少しずつ丁寧に小さな実績を積み重ね、最終的には地域力の向上という形で団地内全体の活動になって行くことを夢見ています。

















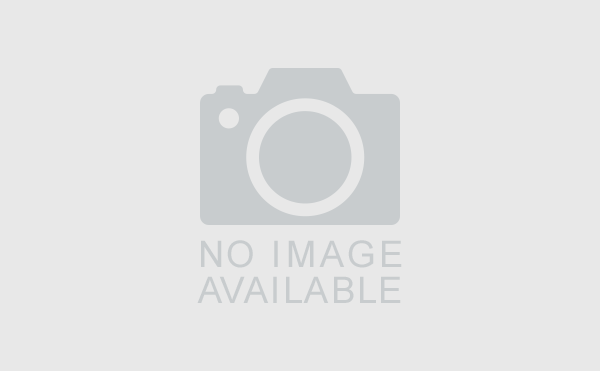
本間先生の地域の『晩酌の会』が、この秋で2周年とのこと、おめでとうございます。
これまでの2年間には晩酌をしながら地域を語り合い、何か自分達で地域を明るくより良く出来ないかと模索しながら活動を進めて来られたのでしょう。
そこには、社会的役割を身近なこととして気負わずに参加できる様な秘訣でもあったのでしょうか。
「おせっかいcafe」「剪定教室」と、ひとつずつ活動の幅が拡がる様子は「真似てみたい」と惹かれるものがあります。
私の地域の『縁側日和』も令和5年10月15日のプレオープンから、もう直ぐ2周年になります。
この会を始める前は、私はどんな企画で興味を惹こうかと、参考になりそうな活動を注視したり、あれこれと目新しいことを考えたりしていました。
ところが、所詮田舎町の何も無い地域です。何か他所から借りものをしたとして、息長く活動するには無理があると気づいたのでした。
実際に私達の活動は、地域のさもないことをことさらにワイワイ、ワクワクと楽しむように過ごして来ました。
「オレンジ🍊かふぇ」ですから、認知症の方が躊躇わずに参加出来る居場所です。
でも、実際には後期高齢者を中心に、認知症の家族介護者や、私を含めその予備軍が集っています。どんな人にも塀を立てず自然体で関わり合うこの居場所こそ、これからの認知症に備えた関わりを身につける場になるのではないかと考えます。
私達の課題は、この関わりを次世代に繋ぐことです。
高齢者との時間には限りがあり、毎回その時を精一杯楽しむことが何よりの時間となっています。櫛の歯が欠けるように少しずつ寂しくなる前に、ひとりでも多くの新しい仲間を増やしていきたいものです。
その時を楽しみに、これからもワクワクと地域を満喫していきます!
同時期にスタートした『晩酌の会』からは今後も目が離せないです!
またご報告をお聞かせください!