無事に自宅に戻る
2年前の今日(5月6日)は、四国八十八ヶ寺歩きお遍路の全日程を終え、自宅に戻った日です。
あの時から二年の時間が過ぎています。2年というと、ほんの少し前のような気がするのですが、私の中では遠い過去の出来事のように思えます。
四国八十八ヶ寺歩きお遍路を終えて、何か変わったかというと、ほとんど以前と同じ日常を過ごしているような気がしています。こう書くと、お遍路に投下した資金と時間は無駄だったのかと思われるかも知れません。私としては、こうした感覚が「而今」(今を精一杯生きる)に通じるように思えます。こうした感覚こそが、四国八十八ヶ寺歩きお遍路で得た学びのように思えます。
四国八十八ヶ寺歩きお遍路の第一日目3月13日から今日5月6日の帰還までの期間約2ヶ月は、様々な事柄を内省する(自分自身の考え・心の状態や行動などについて深く省みること)期間と自分では考えています。
仏教の修行で、常坐三昧(じょうざざんまい)というのがあります。90日間、食事とお手洗い以外は、ひたすら坐禅をします。ただし眠気などに悩まされた時は、仏名を唱えることが許されます。
また、仏教では安居(あんご)という習慣もありました(後のお寺の原型ともいわれている)。修行者達が一定期間一箇所に集団生活をし、外出を避けて修行に専念すること、また、その期間をいいます。雨期のある夏に行うことから、夏安居(げあんご)、雨安居(うあんご)とも呼ばれたりします。インドでは春から夏にかけて約3ヶ月続く雨季の間は、外出が不便であり、またこの期間に外出すると草木の若芽を踏んだり、昆虫類を殺傷することが多いので、外出しないでお堂に籠もるこの制度がはじまったとされます。

(仙台空港では思いもよらないお出迎えを頂き感激しました)
私も、時期的には少し早いのですが、四国八十八ヶ寺歩きお遍路に行っていた期間は、是に習って「安居(あんご)」していると思っても良いのかもしれません。
なんちゃって「安居」の期間に、曹洞宗の開祖道元が書いた「正法眼蔵」の解説本を読みました(NHK100分で名著『正眼眼蔵』1000円+税)。「正法眼蔵」は難解な本として知られ、佛教ではなく哲学書だとも言われているのですが、私のも分かるように解説しています。
その中で、「修行」する意味について書かれていた箇所がありました。道元がまだ若い頃、「お釈迦様は、人間には誰にでも仏心(仏のこころ)が宿っていると言われている。それなら、なぜ修行が必要なのかと悩んだ」とあり、その中で辿り着いた考え方が書いてあります。
仏性があっても、そのままではことは起こせない。なので、持っている仏性を仏性として活性化させるために「修行」が必要なのだと言います。別の言い方をすれば、私たちは、自分が持っている仏性を修行によって「活性化」させることが出来る。だから、修行に励みなさいと!
そして、修行して仏性が活性化すると、悪事やこだわり等々が自然と私たちから遠ざかって行くのだとも言います。修行を行うことで、煩悩を打ち消すというのはではなく、修行で仏心が活性化すると、煩悩の方が私たちから遠ざかっていくのだそうです。私は、この下りがとても腑に落ちています。
とはいっても、私はまだまだ煩悩や執着に取り憑かれています。全く修行が足りないようで仏性が活性化していません。毎朝の歩き行を続けないと。


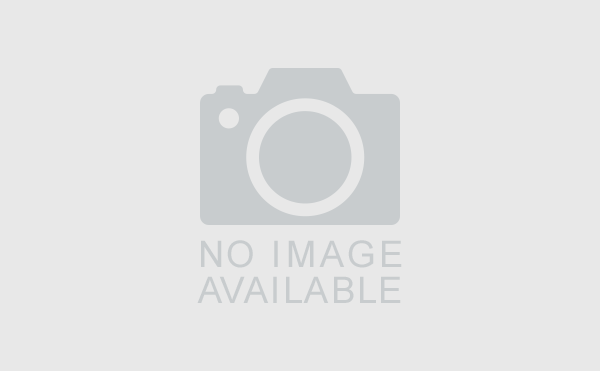
ひとたび家から出たら何が起こるかわからない、まさに修行ですね。
誰もが外で何かしらの刺激や苦労やアクシデントを経験した後「無事に自宅に戻る」のです。
「ただいま(帰りました)」このひと言と同時に背中の荷物を降ろし緊張を解いて、「やっぱり家がいちばん」と、あたりまえの日常に戻っていきます。
『無事に自宅に戻る』ことこそ修行の締めくくりなのかも知れません。
そういえば子供の頃、遠足などの非日常の解散時には先生が「家に戻るまでが遠足ですよ、気をつけて帰りなさい」なんて決まり文句のように言われていましたっけ。
先生は四国八十八ヶ寺歩きお遍路を息も絶え絶えになりながら結願されましたが、あれほど過酷な修行でも命有って帰れれば、それは「無事」と言えるのですね。
その日の「ただいま帰りました」には、心からの「ご無事におかえりなさいませ」が返ってきたことでしょう。
そんな温かい場面をおもい浮かべました。
それにしても見事な二輪草と水仙のお花畑をご紹介くださって、ありがとうございました!