みんなの学校 講座名『保健体育』
『健康』について(2025-04-21)
(今講座の趣旨) 毎月第三月曜日は『保健体育』の時間です。
この講座では、健康的な暮らしの営みに資する様々な知見・智慧を学びます。皆さんのセルフケアスキルを高めるための生活の知恵や最新情報を探し、お届けしていきたいと思っています。
そうは言っても、私は医師でも健康づくりのプロでもありません。この為、私の持っている知識を生かしてお話しするということではなく、ちまたに溢れる様々な情報を取捨選択して皆様にお伝えし、同時に皆様からの情報を多くの皆さんと共有するという方法で学びを広めそして深めているきっかけ作りの場にしていきたいと思っています。
(はじめに) 多くの人々にとって、健康はとても大切なテーマです。また、子どもを気遣うときや大切な人を想うとき、「くれぐれも健康には気をつけて」等々が常とう句(一定の場面において良く使われる言葉)となっています(そういえば、Mr.Childrenの楽曲に「常套句」というのがありますね。「常とう句」のイメージを掴むに役立つかも)。
私たちは、日常的に「健康」を語る機会がとても多いように思います。でも何処かネガティブな視点で語られていることが多いように感じています。歳を重ねると尚更この傾向が強くて、時として「健康」が不安をかき立てる脅迫にも近い形で使われていることが、とても気になるのです。
このような様子をみるにつけ、「健康」について、チョットだけ立ち止まって「そもそも健康て何だっけ!」って皆さんと考えてみたいのです。これは、この講座を開始するに当たって、「健康」を初めに取り上げる一番の理由です。
(「健康」の定義) 普段使いの「健康」は、多くの場合その反対語は「病気」のように使われているように思います。この様な使い方は間違いではありませんが、「健康」の意味はもう少し広く多様なようです。ここでWHO(世界保健機構)の健康の定義を紐解いてみます。
戦後初めて国際的に明示され、現代においても幅広く引用されている健康の定義は、1948(昭和23)年の世界保健機関(WHO)憲章前文「健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。(Health is a state of complete, physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity)」です。
WHOの後年の文書や議論において、この健康の概念は多くの議論が重ねられ変遷を遂げて来ています。このことは、社会情勢や人々の生活スタイル等々によって状況が変わってきていることを意味しています。
代表的な議論(提案)を挙げてみます。1986(昭和61)年のオタワ憲章では、「身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態に到達するためには、個人・集団は成したい事を定義し、実現し、ニーズを満たし、周囲の環境を変えたり対処したりすることが出来なければならない。そのため、健康は目的ではなく日々の生活の資源と見なされる」と記載されています。
さらに、2010(平成22)年のアデレード声明では、「健康とは、人の身体的能力に加え、その人の持つ社会的および個人的なリソースにも重点を置く、ポジティブな概念」であるとの記載がなされています。
すなわち、WHOの定義に端を発した様々な議論は、健康の概念は、「静的な状態」としての健康から「動的な資源・能力」としての健康へ、さらに個人の身体にとどまらず社会的な資源にまでその射程が広がっているのです。社会学を学ぶ一人としては、こうした議論の方向性は、とても良い方向に向いていると思っています。
2011(平成23)年には、オランダのマフトルド・フーバー氏による「Positive Health」(前向きな健康)概念が提案されています。健康の定義を、
①現行の健康の定義にある「Complete」の文言が意図せず医療の範囲を拡大してしまう。
②人口および疾病構造が変化し、慢性疾患と障がいを持つ人々が決定的に病気であるとすることは、システムの持続可能性の逆効果となる。
③「Complete」な状態は測定も運用も不可能であるため、定義は実現不可能なものに据え置かれてしまう。
これらの点を挙げて批判しています。その上で彼は、健康を「社会的・身体的・感情的課題に直面した際に適応し、自ら管理する能力」と、定義したのです。
日本の識者は、フーバー氏の指摘した問題点の②は、日本において決定的に当てはまると指摘。疾病構造・人口動態の変化から社会保障費は増大を続け、医療現場のリソース(使える資源)はひっ迫している。だとすれば「完全な状態」(Complete)を追い求める健康観から、自身の成したいことを定義し、社会的・身体的・感情的課題に直面した際に適応し、自ら管理する「セルフマネジメント」によって成したいことを実現する能力を涵養する健康観への転換が必要と考えるべきだろうと語っています。
(「健康の積極的誤訳」)
私個人の考え方を下にして積極的な誤訳で健康を整理してみます。誤解を恐れず、極めて簡単に表現すれば、この定義の変遷の方向性の特徴は、健康のとらえ方を、身体疾患の治療を中心とする「医学モデル」から「心理社会モデル」に基づいて理解しよとする考え方を明確にした所にあります。以後、心理社会モデルの立場からの健康(身体的、精神的、社会的)を連想しやすい様にする為に「健康」から「ウェルビーイング」(well-being)へと呼ぶことが好まれるようになってきました。
このような考え方(意識)の変化は、医療の目標を病気の治療から健康の増進という幅広い活動へ向かわせるものにもなっています。
成人病」から「生活習慣病」へと名称変更が成されていることはご承知のとおりです。また、生活の質(QOL: Quality of Life)の概念の広がり等々、「健康」のとらえ方は、「医学モデル」から「心理社会モデル」と変わり、社会的要因や心理的要因を抜きには考えられなくなって来ています。
この様に、「健康」vs「病気」ではないのだと整理し、そこには、社会・他者との関わりを下にした積極的な暮らし方が介在して「健康」があるのだと理解しています。
(健康の構成要素「国際生活機能分類(ICF)」)
少し「健康の定義」から離れて健康について考えてみます。
国際生活機能分類(ICF)には、「健康」との向き合い方が示されています。2001(平成13)、WHO総会で国際生活機能分類(ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health)が採択されました。ICFは、健康の構成要素を分類したものです。
健康の定義は変えられていませんが、新しい健康観を提案しています。そこでは,半健康な状態にある人も含め、個人の生活機能に焦点が当てられ、それを発揮することで、より良い状態を実現することができると考えられています。
国際生活機能分類(ICF)以前は、国際障害分類(ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps)と呼ばれ、「疾病の帰結に関する分類」といえるものでした。具体的には、①疾患・変調、②機能・形態障害③能力障害④社会的不利が構成要素です。これは、必要な支援をネガティブな側面にその中心を置いて整理されています。
これに対して、新たな国際生活機能分類(ICF)では、健康状態を構成するものとして①心身機能・身体構造②活動③参加と、いう生活機能のポジティブな側面に視点が置かれて整理され、それらを支える背景因子として、④個人因子と⑤環境因子とが挙げられています。
この考え方は、疾患や変調に伴って生じる障害に対して、個々人のもつストレングス(強みや長所)やポジティブ(前向きな考え方)な特性からアプローチする方向性を明確にしています。さらに、専門家や支援者の役割は、障害や困難をICDに基づいて把握するだけではなく、その人の日常生活の質(QOL)を高めるための機能や資源に注目し、対象者のストレングス発揮を支援することとしています。簡単に言えば、「対象者の良いところを見つけ引き出して自律を支える」ことです。
ICF等というと小難しいのですが、東日本大震災で被災者支援が行われていたときに、「相手に寄り添い、持っている良いところを引き出し、それを支えていく。それが自律支援!」。耳にタコができるほど言われていた内容と同じことです。

上記図は、様々な資料を下に筆者が加除修正を加えて作成しています。
参考にした資料(出典)
・日本WHO協会 https://japan-who.or.jp/about/who-what/charter/(20250418)
いつもながら少々くどい話になってしまいました。最終的には、WHO(世界保健機構)の健康の定義に戻ります。「健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」
健康とは、病気でないことか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そしてなにより社会的にも、このすべてが満たされた状態にあることをいいます。身体、心そして社会という三つの輪が重なり合ったところに「健康」があると言うことです。
私たちは、この「健康」とい考え方を下にした暮らしの営みを今一度考えてみる必要があります。そうすると、がんに罹患し経過観察中なので「健康ではない」と思っていた自分は、必ずしもそうではないかも!と思えたり、反対に病気なんかしていないから健康の不安はないと豪語し、「他者との関わりを閉ざし、独りよがりの生活をしている」のはマズいかも!と思えるのではないかと考えるのです。病気(疾病)との向き合い方や病気を抱えながらの生活に、少しだけ前向きになれる機会になればこの記事「健康」を書く意味が見いだせるような気がします。
今日この機会に、日々の過ごし方がもう少し穏やかでそして社会的存在としての暮らしの営みが皆さんの健康を推し進めてくれることを願って今日のお話しを終わりにします。


「おせっかいCafe」(最高齢86歳)2025-04-19
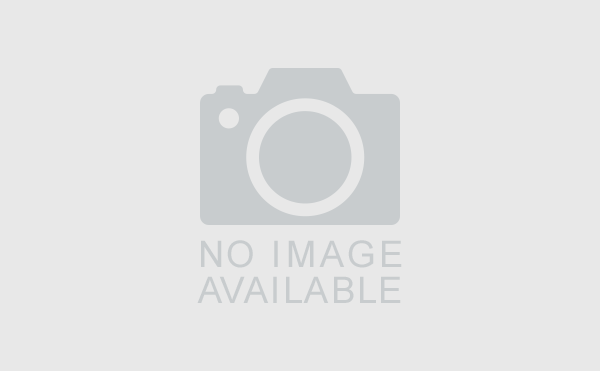
「健康」について頭で考えだすと、何を支点に考えたらいいのかなど迷路にはまってしまいそうな自分がいます。
私個人としては「理想」が心にあることはとても良いことだと感じています。ドキュメンタリー映画「人生フルーツ」を見て以来(何度観たことか!)私の中にひとつの理想ができました。映画のサイトを見ると「津端修一さん90歳、英子さん87歳、風邪と雑木林と建築家夫婦の物語」となっています。90歳の修一さんが颯爽と自転車を乗りこなして自分で描いた絵ハガキを出しに行く姿、仕事を頼まれたらいつでもすぐに対応できるように自分を準備していた姿、最後のその日も草取りをしてちょっと昼寝・・・そうやって眠るように旅立った姿などがありありと心に浮かび、そのたびに限りない希望の光を感じます。
映画に出てくる言葉「むかし、ある建築家が言った。長く生きるほど、人生はより美しくなる。」というその言葉を、私自身も心から言えるようであること、それが理想です。そのためにはどうしたらいいかな、と日々考えて行動することが私にとってすごく大事なことだと感じています。
これが私にとって一番わかりやすい「健やかさ」かな、と記事を読んで思いました。
いろいろな健康の定義があるのだと思いました。
ゆっくり読み進め、それはどのようなことなのだろうとイメージし、自分に当てはめていったときに、最後に先生が書かれていた「健康とは、病気でないとか、弱っていないとかいうことではなく、肉体的にも精神的にも社会的にも、このすべてが満たされた状態にあることをいいます。」が、結局ストンと自分の中で腑に落ちました。
完全に良好な状態という言い方より、すべてが満たされた状態という表現の方が「そうなのよね~」と思います。
でも、いつか『完全に良好な状態』という意味も理解できるようになるのかもしれません。
私は、「その人が心地よいと感じているか、満足してしあわせな気持ちになっているか」ということが、健康にはすごく大切なように思っているのですが、加除修正いただいた生活機能モデルの図を改めて見て、土台には環境因子と個人因子があり、それらは、心と体、生活行為、役割や社会参加などの生活機能(生きること全体)に影響し、その結果、元気に過ごせたり、落ち込んだり、病気なったりすることもある、そしてそれはまた自分の生活機能に影響していく・・というふうに理解しました。
私は今、環境因子に変化があり、心が落ち込んでいる状態です。
目の前にどんなにごちそうがあっても、ワインを数本買いこんでも心がときめかない!
これはちょっと・・・変。
こんな時は健康とは言わない?いや、当たり前の反応をしているから健康であり、それをなんとかしようと活動を変えたりするのかもしれません。
それができれば健康?
すべてが満たされた状態VS健康状態(病気、怪我、ストレス等)
う~ん、面白くなってきました。
来週も楽しみにしています。
『そもそも健康って何だっけ?』
普段,「健康」という言葉はよく使っていますが,あらためて考えてみるとなかなか言葉であらわすのって難しいな・・と思いました。
心(精神)も身体も良好な状態って,結局,その人がどう感じているのか,ということなのではないのだろうかとも思います。
これからみなさんと一緒に学んでいきたいです。
どうぞ,よろしくお願いいたします。
『保健体育』の講座をありがとうございます。
福祉を学び始めた頃に、「健康とは…」と講義を受けていたにも関わらず、目先の不安に囚われていろんなことに自分で限界を決めてしまっていた時期があったなぁと振り返っています。
定期的に通院が必要であっても、自分が自分であることを感じて自分らしくいきいきといられる。心通わせ合える仲間たちや、大切な人と季節のうつろいを感じながら時を過ごすことができ、仕事や地域での役割りを通じて社会参加の機会を与えていただけている今、「健康だ」と感じられる喜びを噛みしめています。
保健体育講座第一回目は、「健康」を意識して暮らすことを学ばせていただきました。
桜前線が通り過ぎ、新たな芽吹きの季節に向かって一歩を踏み出せるような、清々しい気持ちになりました。
ありがとうございました。
『健康』とは、誰にとっても最も身近で大事な関心事です。
そしてその定義は、世の中の変化や人々の価値観の変化により変わってきているのですね。
最新のWHO(世界保健機構)の定義では「健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」と謳われているとのこと。
確かに「身体的、精神的、社会的に」と3本柱で定義付けられていることには納得します。しかし、「完全に良好な状態」とは??と、ちょっと考えてみました。
私は、その身体的、精神的、社会的な3本柱がバランス良く成り立っていることが個々人が健康な状態と言えるのではないかと考えます。
その3本柱による三角形が大きくても小さくても、出来るだけ正三角形に近いのが良いのではないでしょうか。さらに、それを整えるのは自分自身でも良いし、もちろん誰かの支えによって整えられても良いでしょう。
一人ひとりが自身の健やかな日々に感謝が持てて、さらには、その余力で家族や隣人の健やかさを祈れるようだと素敵な関わりのある人間関係が築けそうです。
先ず大切にしなければならないのは自分自身、それがあればこその他者への支援です。
私達は歳を重ねるごとに右肩下がりの健康状態ですが、それが出来るだけ緩やかな下降線で描けるよう、自分にピッタリな楽しみのある生活習慣で毎日を過ごしていきましょう!
そうだ、それがいいと思います!