講座『民生委員児童委員私論』
はじめに(講座の意図・目的)
私たちが暮らす地域社会は、人口構造や就業構造の変化等々を背景に、長い時間をかけて家族関係にも変化をもたらし、「遠くの身内より近くの他人」が現実となっています。こうした社会背景から、私たちが暮らす地域社会は、戦後からの復旧・復興や多くの子どもで溢れていた頃の自然発生的に行われていた近隣関係を下にした「相互扶助」(お互い様)とは異なる、今日的課題を下にした近隣関係そして相互扶助(お互い様)が大切になっています。そうした地域社会の現状を見たとき、地域福祉推進の一端を担っている民生委員児童委員の役割はとても大きいような気がしています。
民生委員児童委員の役割が大きくなっている理由を大きく二つ挙げてみます。
其の一 社会福祉に関わる様々な制度の充実と伴に、それらを上手く使うあるいは繋がるための知識「制度活用リテラシー」(リテラシー(literacy)とは、元々「読み書きの能力」を表す言葉でした。現在は「ある分野に関する知識やそれを活用する能力」のことを指しています。)が必要になっています。特に日本は、制度利用は「申請主義」を基にしているので尚更「制度利用リテラシー」が必須なのです。この為、本人・家族の「制度活用リテラシー」へのお手伝い場面が多くなってきています。
其の二 制度が充実してきているとは言え、その制度は何らかの生活苦(普段の生活の継続に支障を来す困難)を対象としており、日常生活上の困りごとの対応は、家族内での対応・解決が前提です。「補完性の原則」という豊かな生活を目指し福祉(障害)に立ち向かうときの担い手の考え方があります。始めは「本人」(自助)次が「家族」(互助)、そして「地域社会」(共助)最後に「行政」(公助)という順番で立ち向かい支えていくという考え方です。本人・家族の頑張りを地域が支えるという構図は、「遠くの身内より近くの他人」という現状下で、より近隣の方々の役割が多くなっています。
こうした地域社会の現状を基にして、何らかの課題を抱えている方々とその解決手段を持っている行政や社会資源(地域社会も含む)をつなぐ役割として、民生委員児童委員の出番が期待されているのです。
民生委員児童委員活動の基本は、この「つなぐ」です。決して民生委員児童委員自身が、主体的に課題解決のために奔走することではありません。
しかし、民生委員児童委員に向けられる期待は、過剰と思える程負担が大きいのも現実です。この「期待」は、地域住民からは「困りごとは何でもやってくれる」という誤解、行政からは「何の情報提供もないままのお願い」という体の良い下請け要請、そして地域社会からは、様々な地域活動の役員という充職、という形で「期待」されています。
こうした民生委員児童委員への期待?が、過剰と思える程負担が大きい現実を生み出していると考えています。
こうしたことから、もう少し過度な負担とならないでその役割を担える術を、試行錯誤にはなりますが考えていきたいと思っています。また、「民生委員は大変」と、知れ渡っていることから、そのなり手が不足し、欠員も出ています。こうした状況に対処するために、何とか新たな担い手を見いだすべく、「民生委員をやっても良いかな」って思って頂けるような学びの機会を設けたいと思っています。こうした想いから、現職のリカレント教育・スキルアップ及び新たな担い手育成を図り、「民生委員児童委員活動の基礎」を学んでいきたいと考えています。
平成29年3月末現在、全国で約23万人の民生委員・児童委員が活動しています。また、その身分は「非常勤特別職地方公務員」で、無給で活動を行っています。この辺のこと中心に関係資料を下にして紐解いていきます。
1 民生委員児童委員制度
(沿革) 民生委員制度は、1917(大正6)年に岡山県で誕生した「済世顧問制度」を始まりとします。翌1918(大正7)年には大阪府で「方面委員制度」が発足し、1928(昭和3)年には方面委員制度が全国に普及しました。1946(昭和21)年、民生委員令の公布により名称が現在の「民生委員」に改められています。この間、一貫して生活困窮者の支援に取り組むとともに、とくに戦後は、時代の変化に応じて新たな活動に取り組むなど、地域の福祉増進のために常に重要な役割を果たしてきました。このように「民生委員児童委員」は、法律に基づいて設置され、地域の福祉増進のために活動していいます。
(身分・報酬) 民生委員児童委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣が委嘱した、その仕事をしている時のみの非常勤特別職地方公務員です(地方公務員法第3条第3項)。また、報酬はありません。ボランティア(無償の行為)として活動しているのです。ただし、必要な交通費・通信費・研修参加費などの費用弁償(活動に要した費用を支払う)の性格を持つ活動費(定額)は支給されます。私の場合は、毎月発行の「民生委員児童委員新聞」及び必要に応じて適時に発行する「民生委員児童委員新聞号外」作成の為のプリンターインク代でほぼ消えてしまい赤字です。
(任期・定年) 任期は3年、再任も可能です。民生委員児童委員を担えるのは原則75歳の誕生日が属する任期迄です(結果として75歳を超えて務めることがあります)。
(守秘義務) 民生委員児童委員活動は、様々な相談を受ける過程で個人の私生活に立ち入ることもあるため、活動上知り得た情報については、厳しい守秘義務が課せられています。この守秘義務は、委員退任後も引き続き課されます。また、その職務に関しては、都道府県の指揮監督及び市区町村の指導を受けます(民生委員法第15条・17条)。
2 主な活動内容(制度で規定している内容)
民生委員児童委員の職務は、民生委員法第14条では次のように規定されています。
《民生委員》
1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
また、児委員・主任児童委員の職務は、児童福祉法第17条では次のように規定されています。
《児童委員》
1.児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
2.児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
3.児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
4.児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
5.児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
6.その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと
ここまでは、民生委員と児童委員を兼ねている民生委員児童委員共通の職責です。次は、主任児童委員限った職責です。
《主任児童委員》
1.児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
2.区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと
3 活動内容の現状
民生委員法等の制度では、この様になっています。これが現実の地域社会においては、高齢者の居場所づくりとなっている「お茶っこサロン」「防犯活動」「通学路の児童誘導」「敬老会事業」等々のお手伝いから独居者の孤独死疑い対応(警察への通報等も含みます)まで際限がないほど広がっています。個人的には、とても疑問を感じる現状です。
行政統計で数字的にみると、分野別では、「高齢者に関すること」が半数を超え、「子どもに関すること」が2割、「障害者に関すること」が1割弱となっています。内容別では、日常的な支援、在宅福祉、健康・保健医療、児童関係など幅広い相談が行われています。
民生委員・児童委員1人の1月当たりの活動は、相談支援件数が約3件、訪問連絡調整回数が約20件、その他の活動件数が約10件で、1月当たりの平均活動日数は11.0日となっています(厚生労働省「平成24年度社会福祉行政業務報告」より作成)。
私の令和6年度実績では、相談支援件数は6.3回/月(年間76件)、その他の活動は、7.3回/月(年間87件)、その他関係機関との連絡調整が3.5回/月(年間42件)です。活動日数は10.6日/月(年間127日)となっています。ほぼ全国平均だと思います。ただこれは、外に出て行った活動だけです。自宅で民生委員児童委員新聞づくりやその為の取材等は算入していません。この為、民生委員児童委員活動に費やしている時間はもっと多いように思います。
4 民生委員児童委員の数
全国の民生委員児童委員は、2022(令和4)年11月30日に3年間の任期が終了し、同年12月1日に一斉に改選(厚生労働大臣委嘱)されました。それによりと以下のようになります。
定 数:240,547人(※令和元年(前回改選時)239,682人)
委嘱数:225,356人 うち新任委員:72,070人(32.0%) 再任委員:153,286人(68.0%)
宮城県は、定数3,144人で、委嘱人数2,847人、欠員267人です。
仙台市は、定数1,621人で、委嘱人数1,489人、欠員132人です。
5 民生委員児童委員になるまでの流れ
民生委員児童委員は、法律に定められた役割を行う、厚生労働大臣から委嘱を受け、無償で活動する非常勤特別職地方公務員で、地域福祉推進の担い手として、生活や福祉全般に関する相談・支援を行っています。
民生委員児童委員は、厚生労働大臣が委嘱します。その上で各市町村長は、担当する地区を委嘱します。
委嘱までの流れは次のようになります。町内会や地区社会福祉協議会、民生委員等の代表から構成される各地区の民生委員候補者選考委員会、各区の民生委員推薦準備会において選出された候補者を、民生委員推薦会、社会福祉審議会民生委員審査専門分科会での審査を経て市長が推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。任期は3年間で、3年に一度一斉改選が行われます。下の図は、委嘱までのフロー図です。

まだまだ書くことがありますが、固い内容でもう皆さんは飽きたと思います。なので、民生委員児童委員の概観はこれくらいにします。次回から、少し具体的な内容を取り上げてみます。嫌がらないで是非お付き合い下さい。
南三陸町で被災者支援を担う「生活支援員」になるべく、駆けつけてくれた町民に三日間の初任者研修をしたときに皆さんに言っていました。「明日も来て下さいね、皆さんの力が南三陸町では必要なんです」って懇願しました。なぜかって。一日目の研修で、そこまで求められることの重さに皆さんうつむいてしまったからです。もう「そんなこと無理だよ、無理、無理」って、言葉にこそ出していませんでしたが、身体全部で言っていました。正にノンバーバルコミュニケーション(非言語コミュニケーション)です。そんな経験があるので、明日ではありませんが、来月の第二月曜日の訪問を心からお待ちしています。


❸の「委員」「委員会の構成員の職」については、たとえば、自治体における監査委員、人事委員会の委員、教育委員会の委員、公安委員会の委員、収用委員会の委員が挙げられます。地域の民生委員は、ここでいう「委員」に含まれるため、特別職の地方公務員です。

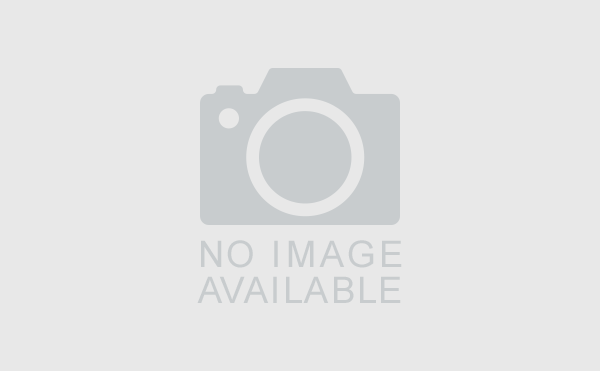
『みんなの学校』の開校,ありがとうございます。
そして,第一回目の講座『民生委員児童委員私論』は,大変興味深く,というか,深刻な思いで読ませていただきました。
今回の記事でいろいろな現状が頭をよぎりました。
うちは兄夫婦がいたので,私は月に1度程度,宮城の実家に車を二時間ほど走らせ,顔を見に行くくらいでも良かったけど,もしも年老いた(今は亡き)両親だけで遠く離れて暮らしていたなら,先生が書かれていた『遠くの身内より近くの他人』に頼るしかなかったかと思います。
2年前に今住んでいる地域に越してきましたが,「なんとかしなければならない」という地区の民生児童員さんの声を聞きながら何もすることができずに,お一人でお亡くなりになったかたもいらっしゃいます。
私の住んでいる所は,隣組と言われる世帯は12しかなく,最近1世帯増えたことを回覧版で知りましたが,私はその方がどこに越してきたのかもわからない状況。おしゃべりするのは決まった人,数人だけです。
そう,行事があれば出かけ,希薄というわけではないのですが,ご近所づきあいというのにはまだまだ遠いかな・・という感じです。
こんな私に,昨年,「民生児童委員になってはいただけないか」と現民生児童委員の方から声をかけていただきました。仕事をしていることと一番はあまりに地域のことを知らなすぎるという理由で,今回は難しい・・とお断りをさせていただきました。でも,ふらっとさんはお仕事をしているときに始められたとのこと,また,地域は回りながら覚えていけるんだよなと,今思いました。
本間先生は,それこそずっとお仕事をなさってきての民生児童委員のお仕事をなさっているのですよね。それまで,ご自分の地域のことはどれくらい御存知だったのでしょうか?
ソーシャルキャピタルという,とても懐かしくもあり,新鮮でもあるスライドが出てきました。私は今はまず,人見知りだなんて言ってないで地域の集まりには積極的に参加し,まずは地域を,人を知ることからやっていきたい。そして,私も,補完性の原則の一員として,そのことで民生児童委員のみなさんの負担が軽減されたり,もっと暮らしやすい地域になれるような役割を担っていけたら・・・と,今回の講座で思いました。
今後の学習が楽しみです。
よろしくお願いいたします。
ハチドリさんの言葉に「地域は回りながら覚えていけるんだよな」とありました。
まさにわたしがそのことは通りのことを実践しています。
嫁いでからずっと仕事をしていましたので、地域のことはみんな家族任せ。元気な姑がいるので、今もなお頼りっぱなしです(^_^;)
さらには地域性と言いましょうか、みんなが地域のことが気になってしたかないといった人たちが住んでいるところなのです。
これまで地域に根ざしていなかったわたしなどが民生委員として日を重ねることができているのも、地域のみなさんのおかげです。
地域を回りながら、区長さんはじめ地域のみなさんに育ててもらえているなぁと感じる日々です。
まさにソーシャルキャピタル
地域のことをわからないわたしが、よりわかっている人を頼ることで地域のつながりがより強くなってくるのかとも思ったりしています。身勝手な理屈ですが😅
わたしも大変な人見知りでありますが、地域に支えてもらいながら役割を担っていきたいと思っています。
これからの学習、一緒に楽しみましょう。
ハチドリ様
hpへの投稿有り難うございました。これをみている多くの皆様にも共通する疑問だと思うのでお返事いたします。
質問は「本間先生は,それこそずっとお仕事をなさってきての民生児童委員のお仕事をなさっているのですよね。それまで,ご自分の地域のことはどれくらい御存知だったのでしょうか?」でした。
私は、東日本大震災のあった年まで県職員として務めており、東日本大震災からは南三陸町被災者支援うや大学教員として仕事をしてました。その間は、職場と家の往復だけの生活です。なので、人様にものを言うときは「地域」を語っていましたが、体験としての地域ではなく教科書や論文での地域、即ち「理屈」での地域でした。それでも、自分自身としては、公務員や大学教員の時も、「地域」をとても意識してきたようには思っています。
理由は、父が行政区長をしていて、その様子を見ていたし、大学(学部)に通っていたときかは「社会政策論」等を通して地域・制度と人々の生活の関わりに関心を持っていました。また、南三陸町被災者支援に関わってからは、大学での学び、県職員としての経験、等々をすべて被災者支援につぎ込み、「入り口は被災者支援だが出口は地域福祉」と語り、地域を意識した活動をして来ました。
それでも、私の体験的地域は、とても乏しいものです。自分の住む地域は、「全く」が着くほど知りません。
この様に、自分が住む地域に関しては、地域を歩き回ることさえなかったのが現実です。現在、民生委員児童院として定期的に対象の方のお宅を訪問するときも、地図をみながら歩いている状態です。第一、顔見知りは殆どいません。この様に、私の知っている地域は、制度や資源といった内容で、生活を下にした地域ではありません。
多分、これは初めて民生委員児童委員になった人に共通すると思います。特に会社勤めや男性の方は、ほぼほぼ私と同じような状態だと思います。なので、ハチドリさんのご質問「自分の地域のことはどれくらい知っていたのか」の答えは「殆ど知りません」となります。そんなことでよくやれるね!と思われるでしょう。
でも、そんな状況でも、民生委員児童委員はやれると思っています。大切なのは「知らないことを知っていること」です。知らないから、近隣の方々に教えを請い、近隣の生活のように目をこらします。また、様々な教科書的知識は、実生活に触れることにより、その制度の重みが分かってきます。この様な視点から自分自身の「無知」を振り返ると、教科書的知識もやはり必要で、それに地域生活の実態を重ね合わせることで、制度や仕組みに血が通い体温を感じられるようになるように思っています。
私が今現在やっていることは、これまでの教科書的知識や行政経験を地域生活の中にあてはめて、制度の力と生活の知恵を重ねたその業力で、地域生活の「安心安全」を築いていくことです。まだまだ微力ですが、そんな意識を持っています。先ほど、民生委員児童委員5月号に掲載するために、長命ヶ丘小学校長のインタビューや写真撮影に行ってきたところです。こんな些細なことを積み上げながら「なんちゃって民生委員児童委員」をやっています。
先生、『ハチドリさんのご質問「自分の地域のことはどれくらい知っていたのか」の答えは「殆ど知りません」となります。そんなことでよくやれるね!と思われるでしょう。』に、そんなふうに思わせてしまったのであれば、謝りたいと思います。
すみませんでした!
既に先生がどのような活動をなさっているのか情報を得たり、『小さなおせっかい新聞』を見せていただき、その内容に驚くこともあったので、地域を知らないからと言うのは違うなと思ったので、その確認の意味で敢えて質問をさせていただいたのでした^^;
今朝、車で出勤する時にお会いしたことのない若いお二人がお散歩をしているようでした。車の中から軽く会釈しましたが、もしかしたら新しくこの地域に越して来たと言うのはこの人たちだったのでは?と思い、今度会ったらしっかりご挨拶しようと思いました。
原発事故の影響で一時全員避難の指示が出た地域、避難指示が解除された今、13世帯だけの隣組ですが、ここに住んで良かったなと真に思えるような地域になったらいいな〜と思っています。
民生委員児童委員さんの知り合いもあり、一緒に活動することもありますが、実際にはどのような役割があるのか把握してはいなかったので知りたいと思っていました。こうして教えていただけて、しかも実際に経験している本間先生自身から教えていただけることはありがたく貴重な機会だと思っています。
私の印象としては、地域で何か活動を始める人がいたら「お手伝い要員として真っ先に声がかかる人たち」という感じがしています。「ここでもお会いしましたね」という感じ。それだけでなく、充て職も実際に多く会議への出席も求められる。ですから本文中の『「困りごとは何でもやってくれる」という誤解、行政からは「何の情報提供もないままのお願い」という体の良い下請け要請、そして地域社会からは、様々な地域活動の役員という充職』のところ、頷きながら読みました。ボランティアなのに、行政からも住民からも「なんでも屋」みたいに扱われること、そのことこそが大きな問題なのではないか、と感じます。
そしてそういうことすべてが引き受ける方の善意や優しさの上に成り立っている、そういう資質がある方が引き受けることが多いので、なおさら「困っているなら」「お役に立てるなら」とどんどんやることが膨らんでいく。地域や学校でボランティアで役を引き受けた方たちにも共通のことだと感じます。
責任を持ちながらも「この地域でこのお役目を引き受けて良かった」と思えるようになるにはどうしたらいいのか、これから一緒に学び考えていきたいと思います。
スマイルさんが書かれていたことを読んで,なおさら現状を実感できたように思います。
『責任を持ちながらも「この地域でこのお役目を引き受けて良かった」と思えるようになるにはどうしたらいいのか、これから一緒に学び考えていきたいと思います』ということに,私もどうぞ混ぜてくださいね。
よろしくお願いします!
3年前に民生児童委員を拝命いたしました。
病気のための定期通院や仕事を抱えているわたしにまで打診があるほど、なり手不足という現実がここにあります。
どの自治体でも新人民生児童委員に対して研修が行われるかと思いますが、3年前の研修はWEB研修で質問もできない状況でした。研修を受けたことでさらに不安が募るという事態に陥っていたことが思い出されます。
今回、みんなの学校「民生委員・児童委員講座」が学び直しの機会になると感じています。
我が町の民生児童委員の皆さんにもこの学びの機会をアナウンスしたいと思っております。
5月の第二月曜日、楽しみに訪問させていただきます。(もちろん、第二月曜日以外も訪問させたさていただきます😅)
本間先生、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
ふらっとさん,コロナ禍のときに,しかもお仕事をなさっていた時に,民生児童委員の役割をお引き受けになられたとのこと。大変でしたね!
あの頃はほんとWEB研修ばかりでしたよね。質問もできない状況で研修を受けたことでさらに不安が募るという事態に陥っていたとのこと,とてもわかるような気がします。
ふらっとさんが書かれていたように,このみんなの学校「民生委員・児童委員講座」が,学び直しの機会にきっとなると信じています。私も本間先生のこのホームページは友人たちにも知らせ,見てもらっていますが,ふらっとさんのお知り合いの民生児童員の皆さまにもぜひお目を通していただけたら,これからの活動や考え方のいろいろな参考になっていくのではないでしょうかね。
ハチドリさん
こうした学びの機会を同じ地域で活動を共にするもの同士が共有できるということは願ってもないことだと思います。
基礎がしっかりしていなければ、応用は効きません。基礎をしっかり学ぶことで自信につながっていくのだと思います。
民生児童委員としての活動を「頼まれたから仕方なく」ではなく、能動的に取り組むきっかけにもなろうかと思っています。
「民生児童委員講座」の広報活動、頑張ります(^-^)
ふらっとさん、本当にそう思います!
あ〜、なんだかとても嬉しい気持ちになっています。
『みんなの学校』1回目の講義からいきなりの内容充実で、昼休みに一度読んだくらいで理解出来るようなものではありませんでした💦
先生の民生委員児童委員の活動について時々お話を聞かせて頂きますが、私はその役割についてさらに詳しく調べてみたことがありませんでした。それは私自身がお世話になるつもりが無く、どこか他人事と考えていたということでしょう。
民生委員とは地域の気がかり案件に気づき、必要に応じて行政の専門機関に繋ぐ役割を担っているのですね。
困りごとを抱える地域住民にとっては身近な相談相手となり得ます。そして行政機関からすれば手となり足となり、地域の隅々まで目が行き届き、本当に公助を必要とする人を選別して繋いでくれる協力者なのですね。
この様な重要な役割でありながら無給とは驚きです。
その為なのでしょうか、私の知る民生委員さんにはふたつのタイプがある様です。一生懸命に地域の気がかり家庭に足を運び、よく話を聞いて、絡まった糸を解すような関わりをする方が居る一方で、地域活動には無関心であまり姿も見かけないという残念な委員さんもいらっしゃる。
でも、この様な印象さえも私個人の民生委員への期待値が高過ぎるということかもしれませんね。
今回、民生委員児童委員の役割について学んだら、これは被災者生活支援員のしていた事と重なる事に気がつきました。
先ずは地域内の日常の様子を知ることから始め、小さな変化に気がつく。さらに注意深く様子を見て、話を聴き、関係機関や専門職に繋ぐ。
民生委員児童委員、それは地域と共に生きることそのものです。この尊い役割がよく理解され、欠員無く必要な委員数が確保されることを願います。
今回の講義で私の地域の民生委員との連携をもっと密にしよう、私の小さな気づきも普段から共有出来るよう、こちらからもっと絡まって良い関係性を築いておきたいと思います。
ありがとうございました。
「民生児童委員さんてそんなに大変なの?」と,先生が今回書いてくれた内容を読んでいて,『これは被災者生活支援員のしていた事と重なる事に気がつきました』という鈴虫さんの言葉を見て,実は地域には被災時とかではなく,普段の時から生活支援員さんのような人がいてもいいのかも・・と思ってしまいました。
ハチドリさん
「実は地域には被災時とかではなく,普段の時から生活支援員さんのような人がいてもいいのかも」
そうですよね。
そして私は、被災時の支援員よりずっと以前から地域に目配りしてくれていた民生委員さんという存在に、今更ながら感謝の気持ちになりました。
振り返れば支援員の時、定期的に民生委員さんとミーティングを開き「気がかりな事案」の情報を共有していました。その際、民生委員さんから「私達は個人情報の壁があって、あまり立ち入ることが出来ないので情報を貰うと助かります」と話されました。
そんなことを思い出したら、やっぱり私もご近所の様子を気にかけ、何か気づきや違和感を持った時には民生委員さんにお話しようと思います。
一人ひとりの意識が高まるように、「地域全体の安心安全をみんなで作り上げていくのがいいですね」と縁側日和でもみなさんに伝え続けていきます。
民生委員さんのお話から自分事へと良い循環が出来そうです。
ありがとうございます。