民生委員児童委員試論第2講『一般的な活動内容』
今日は、前回の民生委員制度の概要に続き、具体的活動内容について触れます。ここでは、「一般的」と書いてある様に、活動内容が事細かに指定されているわけではないので、一般的にこうしたことが行われているという意味で一般的と書いています。
ここで書いているのは、「一般的内容」の標準ということではありません。あくまで、私の考える民生委員児童委員として必要と思っている活動内容です。なので、現職の民生委員児童委員からすると「え~・・・、そうなんですか~???」と言われてしまうかも知れないので、決して標準的な内容とは受け止めず、「本間がやって内容」に留めて下さい。以下、箇条書きで列挙します。
①気がかりな世帯(高齢独居・老老二人世帯)を中心に、各戸を直接訪問して様子を把握する。
②各戸を訪問することなく、担当区域を周り、生活環境に課題がないかどうかを確認する。
③定期的な訪問で把握した課題や漠然とした不安に応えるべく、別途その対象者宅を訪問し、判断に資する情報や資料を提供する。
④毎月1回開催される民生委員児童委員協議会に参加し、行政からの連絡や地区内の情報を共有する。
⑤長命ヶ丘団地内にある福祉施設や各種社会資源が行う制度に基づく会議に出席する。
⑥地域福祉推進に資する活動に参加。
⑦包括支援センターや地区社協等々との連携協働による地域の安全安心に資する事業に参加。
⑧行政や福祉関係機関への情報提供及び情報の共有。
⑨行政及び福祉関連からの求めに応じて地域生活実態の把握及び報告
⑩民生委員児童委員新聞の発行
大まかに箇条書きに活動内容を列記しました。各項目の詳細は、来月に行います。その際、なぜその様なやり方をしているのかなどについても触れます。
これらの活動は、行政や福祉関係機関との連携協働のもと進められます。一般によく使われる「連携協働」や「情報の共有」は、現実の活動においては、とても悩ましい状況もあります。また、この2点に関しては、民生委員児童委員個々人の解釈に開きがあり、必ずしも一様ではありません。それは、必ずしも悪いことではなく、それぞれの経験やスキル等々が下になって行われています。
私も、これまでの行政経験大学院で学んだことそして地域に皆さんか教えてもらったことが下になって民生委員児童委員活動を行っています。なので、多少の違いは当然なのです。次回、その多少の違いの趣旨を含めてお話しさせてもらいます。
蛇足 先日(5月11日)の晩酌の会を仙台放送から取材を受けました。また、来る15日は町内会主催の「ふれあいサロン」に晩酌の会が「おせっかいCafe」を開店するのですが、その様子も取材され、それをまとめて5月28日(水)18時のニュース枠で特集されると聞きました。なので、数十秒ではなく数分放送されるかも知れません。是非75歳以上の皆さんが楽しく活動し想いを語っている様子を観て下さい。


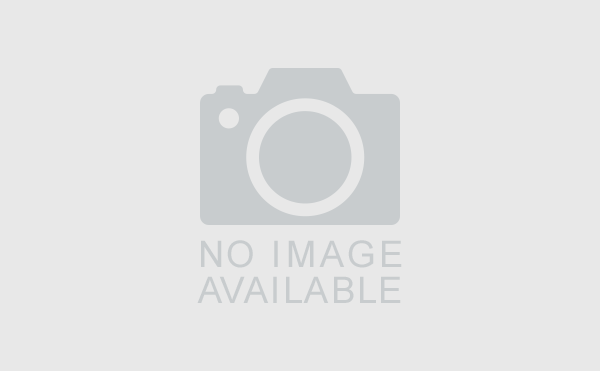
私は宮城県にいた時は、ずっと保健福祉関係の職場に勤務していました。
文中に『これらの活動は、行政や福祉関係機関との連携協力のもと進められます』とありました。
しかし、実際には行政や福祉関係機関が、気がかりな人や世帯をすべて把握しているとは限りません。
さらには受け入れ方や関わり方に差異があることもよくある話です。
ですので、⑧の民生・児童委員さんからの情報提供や住民と顔なじみのある民生・児童委員さんと一緒に訪問させていただいたこと、とてもありがたかったなあ~と思い出しました。
ただしこの話は、合併して大きな市になる前の人口10,000人のちょっとの小さな町での話です。
人口の多い地域での活動はいろいろ大変なことも多いのではないでしょうか。
でも、その分「ああ、良かった・・!」と思われることもたくさんおありだと思います。
③と⑩は、特に本間先生ならではの活動だと思いますが、次回からの詳細の説明、楽しみにしております。
『晩酌の会』や『おせっかいカフェ』の様子が28日仙台放送で流れるのですか?
その日のその時間はテレビを見ることができませんが、見逃し配信で検索して、75歳以上の皆さんの楽しそうな様子をぜひ拝見したいと思います。