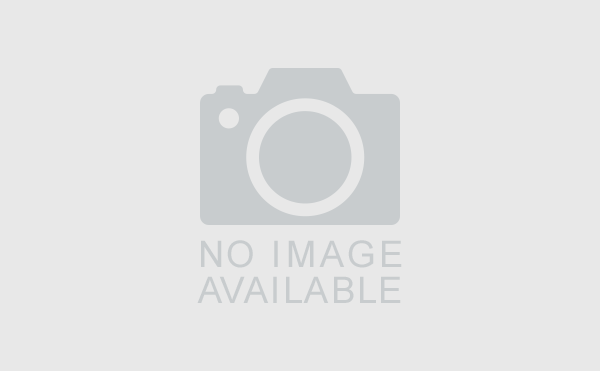様々な学びと思い出を抱えて帰国した留学生へ(続編)
特段の理由もなく、hp地域福祉研究所の管理画面を見ていたところ、「中国」から閲覧があったことを知らせる、世界地図に中国が反転表示されていました。祖国に戻り、読んでくれたのだと、とても嬉しくなりました。
そうしている内に、呼応するかのように、留学生が参与観察及び聞き取り調査でお世話になった方から、中国から「メールが来た」と教えてくれたのです。紹介してもよいとのことなので、皆さんにもお知らせします。
『こんにちは。返信が遅くなってしまい、本当に申し訳ありませんでした。甥が風邪で入院してしまい、最近はとても慌ただしく過ごしておりました😭(今はもう大丈夫です)。本間先生が書いてくださった文章、読ませていただきました。温かい言葉の一つ一つが胸に響き、とても励まされました。マルシェの皆さん、そして本間先生のおかげで、無事に論文を書くことができました。本当にありがとうございます。これからも頑張ります!』というものです。
中国から日本に留学して、日本語で修士論文を書く。これは、私たちが思っているよりもとても大変なことなのです。社会学研究室に籍を置いての修士論文なので、「社会学」の視点で現状と課題を分析し考察しています。数字にものを語らせるのではなく、自らが聞き取り観察した内容と目だけでは分からない日本人の振る舞いの基底にあることを浮き彫りにするのです。文化が異なる留学生には、このような文化を下にした振る舞いを分析することは非常に難しいのです。
修士論文の最終審査では「口頭試問」があります。緊張してとても大変だったと語っていたと聞いていますが、今回のメールでも「無事に論文を書くことができました」とあります。この、簡単な文章には、言い現せない大変な苦労があったことは想像に難くありません。同時に、それを支えた地域の方々の親身になって学業を支えた存在も忘れてはいけません。そこで生まれた相互の関わり合いが、困難を乗り越えられた要因だと思います。
本国で活躍され、日本との架け橋となって、改めて訪日してくれる日を心待ちにして、ご紹介を閉じさせてもらいます。