『35年目のラブレター』を観て
何度か、テレビで見かけた映画を観に行きました。実話を下にした夫婦愛の物語です。
貧しさや家庭環境が故に十分な教育環境を持てず、小学校2年の途中から学校に行けなくなり、読み書きが出来ないまま大人になってしまった主人公。そして彼に寄り添い「あなたの手になる」といってくれた妻の物語です。毎日新聞解説員が彼に寄り添いみてきた風景や抱えてきた思いを一冊の書籍にまとめた。それがこの映画の原作になっている『35年目のラブレター』講談社.です。
彼は、65歳の定年(お寿司屋さんの職人)を機に、65歳になって夜間中学校に入学します。理由は、ただ一つ、寄り添い支えてくれた妻に、クリスマスに感謝のラブレターを書くためです。夜間中学へ入学して5年以上の歳月が経ち、結婚から35年を迎える頃に、ようやくラブレターが形になりかけようとしていた頃・・・・。
私は、多くの方が夫婦愛に感動したのとは少し異なり、ボロボロ涙を流し感動したというよりは、別の感慨に浸りました。彼は、夜間中学校に入る目的を「感謝のラブレターを書くため」と、ただそのことだけを願い通い、長い時間を掛けて卒業しています。その間、彼の人柄は、多くの課題を抱える人々を支えています。それも、凄いことだと思います。それでも、私の視点は、そこではありません。彼は愛する妻に「感謝を伝える為に学校に入った」。では、私は何のために学校に入ったのだろうかと考えてしまったのです。私は、小学校に行けなかったということはさすがにありません。私が中学生の頃は、私の住んでいた田舎では、高校への進学率は6割から7割程度で、まだまだ中卒で都会に就職していく同級生がいっぱいいました。
私自身、中学校2年生までは就職組でした。実家の隣にトタン屋根の屋根葺き職人がいました。そこに弟子入りして板金工になれといわれていたのです。様々な理由で、それを受け入れざるを得ない状況が有りました。その様な中で、確か中学校2年生の秋口だったと記憶しているのですが、担任の先生が親に高校進学を勧めてくれたのです。その様なこともあって、2年生後半から一生懸命受験勉強を始めています。もしあの時、こうしたことが無ければ、私は確実に中卒の板金工です。
東北学院大学経済学部二部経済学科もありません。東北学院大学大学院人間情情報学研究科もありません。東北大学大学院文学研究科人間科学専攻社会学専攻分野編入学も、ましてや博士(文学)もありません。そしてなにより、今、関わっている人達とは絶対会えていません。
映画の主人公が言った、「手になってくれた妻に感謝のラブレターを書く」。私には、これに相当する「学校にいけた理由・学校に行った理由」は、どこにあるのだろうかと考えてしまったのです。中学校卒業だけでは無く、様々な段階で、多くの人との関わりの中で「学校に行け」今があります。その幸運をどう生かせているのだろうかと考えてしまったのです。学校に行けた幸運、そして学校で学んだことをどのように生かしているのか。そのようなことを帰り道で考え、そして今パソコンに向かっています。
当初、大学院に入った時の理由は、経験でだけ物事を判断しない様にしたいという思いからでした。それは、博士課程に編入学してからも同じでした。当時は、長寿社会政策課や地域福祉課に籍を置き、多少なりともその学びを仕事に反映できたと思っています。そして東日本大震災で南三陸町に赴いてからは、「学びを生かしたい」という意識はさらさら無く、元公務員として手をこまねいてはいられなかっただけです。でも、結果的には、大学での学びや県職員としての経験の全てを投入して被災者支援に関わりました。こうした視点では、「学びを生かせた」ように思います。
では、仙台に戻り市井の人となった今、これまでも学びをどのように生かせているのか改めて考えたのです。現在、民生委員児童委員としてのお役目を頂いていることや「遠くの身内より近くの他人」が現実となっている社会目の前にして、大学での学び、県職員としての学び、そして様々な地域活動での経験を生かせるのではないか。生かすべきだと、思ったのです。
彼は、『35年目のラブレター』を書くために、学び、妻だけではなく、多くの人々に希望の窓を開けていた。私は、私のやり方で、様々な課題を持っている地域社会に希望の「窓」を開いていく、そんなお手伝いができるのかも知れない。東北大学社会学研究室でお世話になった先生は、退官記念後援で大学は『窓』だと表現し、その窓に関わっていることに誇りと感謝をもっていました。それなら、私は、これまでの学びを地域社会の安心安全を築く為の「窓」を開くところに学びを生かせれば、これまで多くの人々に支えられ学べた恩返し(恩送り)ができるのかも知れない。今、そのように思っています。
期せずして四月からはhp地域福祉研究所で新シリーズを始めます。これで、初めの一歩を踏み出せるかもしれません。新たに迎える春はもう間近です。なんだか、楽しみというか、自らに課した課題に多少の緊張感を持って日々の暮らしを営めるような気がしてきました。
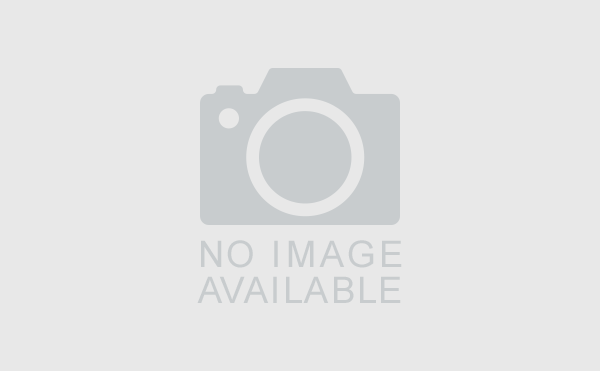
先日、娘と「35年目のラブレター」を見てきました。
たくさんの人から感想を聴いて観にいったのですが、それらも含めて、とても感動しました。もう、私はネタバレ、バレバレの感想を書いちゃいますが、もういいですよね。
映画は、自分が見終わるまでわからない!
観ててまず娘が鼻をすすり、涙を拭くのが横で見えました。
それはのちに奥様となる女性が、彼が作るお寿司を食べて「おいしい」と涙を流すシーンでした。
夜間中学の様子もいろいろな事情の人が来てることがわかりました。
なんといっても担任の先生が「だいじょうぶです!」と言ってくれるのがいい。それを聴いて、私も「きっとダイジョウブ!」と思いました。
とにかくいいなあと思ったのは、すべてが「思いやり」と「やさしさ」に溢れていることでした。
奥さんにラブレターを書いたことがないから「字を覚えたい」と読み書きのできない65歳の主人公が夜間中学に通い始めたこと、やっと書いたラブレターを「もっと学校に行ってほしいから」との理由で『65点』と本人の前で厳しい点数を付けた奥様は、本当は嬉しくて嬉しくてたまらず、隣の部屋で顔をくちゃくちゃにして号泣。
夫婦が毎日交わす、『おはようさん、ありがとさん、おつかれさん』
さんは、太陽のSUNでもある!
三つのSUN、SUN、SUN本当にキラキラして温かいなあ~!
亡き奥様が、生前、丁寧にタイプライターで打った主人公へのラブレターには、『あなたのいいところを三つ書きます。優しい、一生懸命、可愛い』と書かれていました。
ご主人が最後、奥様に渡すことができなかったラブレターには「あなたはいましあわせですか?」と問いかけています。それを見ていなかった奥様が書いたラブレターには「私はいましあわせです」としっかり書かれていて、つながっているとはこういうことを言うんだろうな~と思いました。
1枚の紙にびっしりと書かれていたラブレターを、ご主人はいつのまにかすべてしっかり読むことができていました。
私が一番泣いてしまったのはそこでした。「頑張ったね」と。
もう、いろんなこと、想いがいっぺんに溢れてきて、涙が止まりませんでした。
秦基博の『ずっとつくりかけのラブソング』も最高でした♪
帰りの車で、娘が「いっぱい感動して10回は泣いちゃったな~」と、その場面を振り返っておしゃべりしながら帰ったのも私にはとてもいい時間でした。私は気づいていなかったのですが、娘が「奥さんの最後のラブレターだけど、難しい漢字は使っていなかったよね」と言ったのです。
「そうだったのかもしれない!」
本当の「愛」って、まずは相手のことを心から想うということなんだよねと話をしました。
私がこの映画を観て、学び、やってみたい、やろうと思ったことがあります。
それは、「その人のいいところを三つ見つける」ということです。例え、苦手な人でも・・。
あなたはいましあわせですか?
私はいましあわせです。
あなたのしあわせはわたしのしあわせ。
マドンナ,いい映画のことを教えてくれてありがとう。
ハチドリさんの感想を読んだら又思い出して涙が出てきましたよ。
声出して泣きたくなる場面がたくさんありすぎてね。映画見終わってトイレに行ったら目がまっ赤かったので、お買い物せずに家に帰りました。
自分の親に近い世代のお話しだったけど、相手を思いやる気持ちが本当に伝わって来ていい映画だったよね。苦労しながら仕事を始めた両親の事も思い出しながら見ました。
今はスマホで簡単に文字で送ってコミニケーションしているつもりになっているけど、お互いに毎日の口で話す挨拶や「ありがとうさん、おつかさん」という言葉を聞くと文字で伝えるより言葉で伝える温かさを私も忘れないようにしたいな。
見に行ってくれてありがとう。
また、今度!
私がこの映画を観て一番心に刺さったのは「普通ではないと思いながら生きる辛さ、苦しさ」でした。
月に一度学校に行けないお子さんをお持ちの保護者の方と語り合う会を開催しています。今では隣の部屋に「子どもの居場所」も開設していて、学校にはなかなか行けないけれど、ここに来ることをとても楽しみにし、帰る時には鼻歌になる子もいます。
「普通の人」ってどういう人でしょう?「普通の人」を定義することってできるのかしら?みんな違うから世界は豊かになり、理解しようとするから自分も豊かになるのではないかしら。
印象に残っているシーンは、主人公が握ったお寿司を未来のお嫁さんになる女性が食べるシーン。一口食べて「心がこもっている味」に感動して涙を流す場面。これが恋人でなくてもいい。親でも友人でも、隣のおばちゃんでもいい。その人の本質を見る目を持っている人、本質を受け止めてくれる人がいれば、自分のあるがままで生きていける。そうなれば「普通ではない」ということを引きずって、大切な一生の膨大な時間を辛い気持ち、苦しい気持ち、哀しい気持ちで過ごさずに済むのではないか・・・私も知らないうちに誰かの心に「疎外感」を植え付けてはいないだろうか?
表面的な肩書ではなく本質を見ることができる人、「そういう人に私はなりたい」。そう思った映画でした。
本間先生、私事に紛れてご無沙汰ばかりで失礼しています。
やまぼうしさん、黒かりんとうさん、栗原市民さん、マドンナさん、フラットさん、ご無沙汰しています、お名前拝見出来て嬉しいです。
「35年目のラブレター」を観てきました。
観終えてしみじみ「良い映画だなぁ」と言葉がこぼれました,マドンナさんお知らせありがとうございました。
今を生きる人すべてに「あなたはそのままで良いよ」と告げているような、優しくつつむような物語と感じました。
先日観た「サンセット・サンライズ」も、根底にある人を想う気持ちは相通じるように思います。
映画になるということはそれを求める人がたくさん居るのでしょう、「普通」という幻に苦しみを抱えている人の多さを思いました。
私の父も戦時下のことで尋常高等小学校すら十分には通えなかった辛さを折にふれて話してくれていました、学歴が十分ではないために仕事上の資格も高卒が認定条件の1級は取得することが出来ませんでした。
基本的な教養を身につける機会を失ったことが、思いがけず役職を得た時にどれほど影を落としていたのかは計り知れませんが、定年を迎えた後に役職に就くことを嫌って町工場に一工員として就職し、嬉々として働いていた姿を思い出しました。
一緒に観た友人が「人の本質を見ようとする、そうすれば共に生きる道が開ける」と話してくれたことを心に刻みたいと思います。
追伸です。
「人はいつでも今が1番若いのです」
本間先生、4月からの新シリーズ、楽しみにしています。
マドンナ様
四月からの新シリーズへの応援、有り難うございます。3月10日に発表して以来、58件もの閲覧がありました。
そうした中で、「楽しみにしています」と書いて頂き、木にも登る気持ちでいます。有り難うございます。準備などは特にしていなくて、思い付くままに書こうと思っています。
なので「なんちゃて」レベルの内容になるかも知れませんが大目にみてやって下さい。
追伸
今度、南三陸町に行くようなことがありましたら、お店に立ち寄らせて頂きます。前回行ったときは、「マドンナさんはいますか?」と聞いたら、お店の方々は???でした。是非、皆さんへの周知をお願いします(笑)。
おはようございます。
先生もご覧になったのですね。
私も先日見て、感動しちゃって友だちに「見て」と勧めました。
先生はどうしてラブレターを書くという理由だけで学校に行ったのかという疑問が書かれていました。実は、時代的に戦中に生まれ育って様々な環境から文字を学べなかった人はこの時代なら少なくなかったと今から50年以上も前、小学の時に担任の遠藤幸ニ先生から聞いていたので、文盲の人の話かな、もしくは文字を認識できない障害を持った人の話しかなと思って私は映画を見に行きました。
そしたら、子供の頃から苦労が絶えず充分な愛情ももらえず生き延びてきた人生の中で出会った奥様からもらったラブレターが読めなくて返事も書けずに嘘をつき続けている苦しみがあってずっと主人公なりの努力をずっと続けていたと言う物語でした。
私達は当たり前に字を読んで理解するという生活を送っているけど、定年という節目の時に「今まで生きて生活できていた事に満足するか、忙しくてやり残した事を初めてみようとするかというそれは何歳からでも遅くない」という映画だったと、私は思えて自分の今までの人生でやり残ししている事はないかを考えて始めてみたい事はやってみようと思い映画を見終わりました。
感じ方はいろいろあると思いますが、たくさんの人に見てもらいたいと思いました。
この映画のことをいち早く教えてくれてありがとう。
遠藤幸ニ先生、懐かしいな〜!
『自分の今までの人生でやり残ししている事はないかを考えて、始めてみたい事はやってみようと思い映画を見終わりました』と言う感想、なんて素敵なんだろうと思いました。
私もね、ちょっとやり残していることあるなと思っていて、時間かけてでも少しずつでもやっていこうと思っています。
まだ映画見てないけどね!
先生の記事を読み、鈴虫さんとマドンナのコメントを読み、私も早く見たいなぁと思いました。娘も連れて行って、帰りは美味しいもの食べてこよう!(そこ?笑)
『35年目のラブレター』予告を見て、私も興味を持っていました。
幼少期から読み書きを十分に習えない環境というのがどれ程のものなのか、それは学校に通えないこと以外にも私の過ごしてきた家庭環境とはだいぶ違っていたのだろうと思います。
それでも真面目に仕事で身を立て優しい家族にも恵まれたのは、主人公の人柄と妻の支えがあればこそでしょう。
65歳からの挑戦は、妻に感謝のラブレターを書くために文字を習うこと。なんて素敵な挑戦でしょう。
この動機が素晴らしい。これは「頑張ってー!」と応援したくなります。
「何歳になっても挑戦できる」保さんの姿から大きな勇気を頂き、「私も!」と力が湧き出ます。
じつは私の父も読み書きが十分には出来ませんでした。母が助けて支える姿を見て育ちましたので、それがあたりまえの家庭でした。
父は真面目に仕事に励み、私達家族に静かに愛情をかけてくれました。
私は出かける前に「今日、傘いる?」とたずね、父が空を見上げて「今日は大丈夫」「今日は午後から怪しいから(傘を)持っていけ」とよく当たる天気予報をしてくれていました。
あ〜、お父さんに逢いたくなりました。