高野山を下りる
四国八十八箇寺歩きお遍路を終えて、宿坊で朝を迎えました。朝6時からお勤めがあり、参加しました。
お遍路中は、二箇寺で3回出ましてが、今回無量光院での朝のお勤めは、本格的なものでした。
6時丁度に、山門近くにある梵鐘ではなく、昔火事の時に鳴らされる半鐘の様な鐘が打ち始まりました。其の鐘は、打ち方の間隔や強さを変えながら5分続きました。単なる「合図」ではなく、祈りの言葉のようでした。
鐘を打っていた僧侶が本堂に戻り、所定の場所に座ると同時に読経が始まりました。
僧侶の人数は六人で、主としてお勤めを進める僧侶に従い、読経が進められました。読経は、六人一斉に行うと、その場は一変し、それはそれは神聖な場と化しました。
読経は、主としていた僧侶一人でや六人同時に行う等様々でした。更には、堂内を歩きながら読んだり、その場で立ったり座ったりしながら読んだりと、お経に依って読み方を変えていました。
こうした読経は、休み無しで1時間15分続きました。その間に、一人ひとりの肩に数珠を当てる等して加持祈祷をしてくれました。
私達が唱えたのは、南無大師遍照金剛を5回唱えただけでした。これ程の朝のお勤めは初めてでとてもいい体験をさせて頂きました。
宿坊は、早めに出ました。バス停に行ったら始発まで1時間間があったので、近くの名のしれた仏閣を見て廻りました。それが、添付の写真です。
高野山駅からは、ケーブルカーで下りました。私が、町石古道を8時間かけて登った所を、約10分で極楽橋迄運んでくれました。これをどう受け止めるかは、それぞれの価値観に拠りますが、私としてはまたとないいい体験をさせて頂いたと思っています。
その後は、公共交通機関を使ってスイスイと大阪市街地に戻りました。駅ビルで食べたのは「たこ焼き」です。期待していたのですが、Naritaマルシェで食べたたこ焼きの方が格段に美味かったです。
街なかを菅笠姿で歩くのは少々勇気が入りました。四国では、皆さん「お気をつけて」と声をかけて下さいました。しかし、大都市大阪では、少々「奇異の目」を感じました。
当然ですが、普段の日常に戻って来たことを実感しました。だんだんと、これ迄の日常生活の中に取り込まれて行く感じがします。








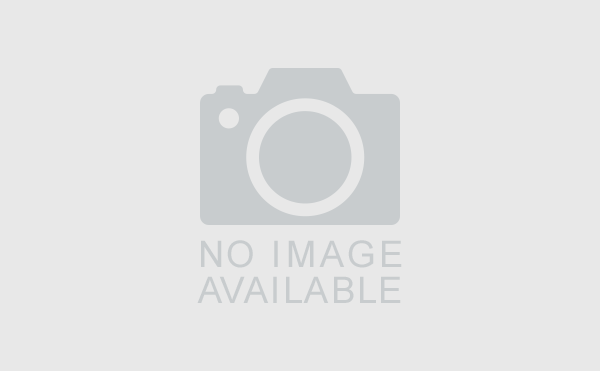
お遍路の締めくくりをまったくの平常心で迎えられた様子に、修行を積むとはそういうことなのかと思っていました。
でも、やっぱり最後の最後に感動のお勤めがありましたね!
自分自身はほんの少しの読経とはいえ、六人の僧侶による心が震えるような読経の中に身を置き加持祈祷をして頂くなんて、これ以上の締めくくりはありませんね。
素晴らしい体験でした👏
その後は、8時間かけて登った町石古道をケーブルカーで10分で下り、公共機関で街まで行きたこ焼きを食べたというその流れには、ちょっと笑ってしまいました。
でも、うしろ髪をひかれずに非日常の精神世界から日常生活に戻るには、それぐらいの潔さが必要なのかもしれませんね。
おかげさまで沢山の擬似体験をさせていただきました。息を呑むようなドキドキハラハラでしたが、とても心に響く紀行文でした。
読み終わってみたら、とても清々しい気持ちです。ありがとうございました。
カンカンカン・・と鐘の音が聴こえました。
今回の歩きお遍路の最後の神聖なお勤め,最後の日にふさわしい,とてもいい時間を送られたようで,良かったですね。先生の中でずっと記憶に残っていかれるのだと思います。
四国では、皆さん「お気をつけて」と声をかけて下さるのに,今日,大阪では、少々「奇異の目」を感じたとのこと。そうかもしれませんね。
でも,わかる人にはわかるし,心の中で手を合わせてくださったかたもいらっしゃるでしょう。先生のお姿を見て,何かを感じとった人もきっといらっしゃるはず。
世の中,そのようなものかもしれません。
私は,今回の先生の四国八十八カ寺歩きお遍路紀行を読ませていただき,そもそもお遍路さんについてやおせったいについてもとても勉強になりました。もしも,目の前にお遍路さんの恰好をしている人が通りかかったら,声をかけて差し上げたいという想いに駆られています。
毎日,本当にお疲れ様でした。
そして,ありがとうございました。
成田マルシェでまた美味しいたこ焼きが食べれるといいですね。
最後に
忘れたという赤い建物は,「高野山 壇上伽藍(だんじょうがらん)」ではないでしょうか?
お大師さまが高野山をご開創された折に真っ先に整備に着手された場所だとか。
余計なことと思いつつ,おせっかいなものですみません。